当ブログは「note」に移行します。
新しい投稿は「note」にアップしています。
フォロー、ブックマーク、RSSでの登録、よろしいお願いします!
1-12.水との繋がり [小説 理想水郷 ウトピアクアの蝶]
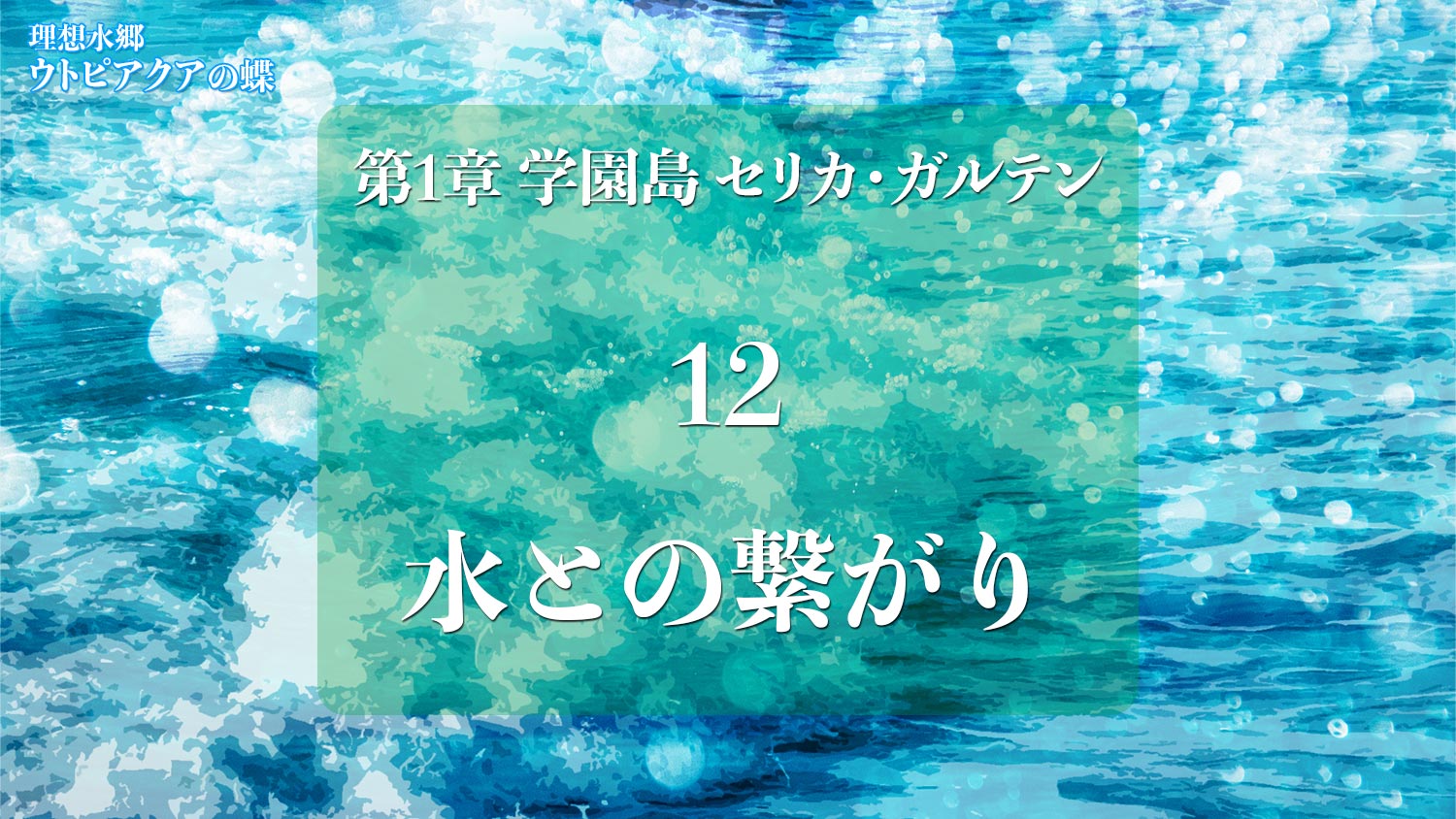
ケイト自らルサルカ派だと切り出し、戸惑うほとり。
水の絵は、十二の精霊による海の怒りを描いたものだった。絵の見え方を話したほとりは笑われた。
そして、セリカ・ガルテンに連れて来られた理由を知る。
踊る水
「もうほとりは、聞いた? 私がルサルカ派だって……」
ケイトの言葉に、ほとりの心臓が一度強く打った。同時に目の前に広がっていた宇宙は、茂みと蛍の現実の光景に変わった。
ほとりは、どう答えていいかわからずそのまま固まった。
「そっか。もしかしたら、夕食のあと来ないんじゃないかと思ってた。でも、ユーリがほとりと相部屋になったって言ってたから、来るかもとも思ってた」
「私は、どっちがいいとかは、本当のところは決まっていなくて……。水の絵の説明は詳しく聞かされていないというのもあって」
「ま、生徒会はインボルク計画を進めているからな」
「でも、あの絵。私には、荒れ狂うようには見えなかった。まるで、水が優雅に踊っているように見えました」
ほとりがそう言うと、ケイトが大いに笑い始めた。ほとりは、自分が変なことを言ったのかと思い返してみたが思い当たらず、ケイトを見つめた。
「許せ、許せ。あの絵を見て、水が優雅に踊っているように見えるなんて言ったやつが今までにいなかったから」
「でも、私にはそうにしか見えなくて」
ほとりの沈んだ表情を見たケイトは、依然笑顔でうなずいた。
「そう見えたなら、そうなんだ。あの二枚の絵は、人によって見え方が変わる。たいていは、水が暴れている絵と言う。でも、ルサルカ派のやつらは、その逆。数は少ないけど」
「あの絵は、ナイアが水で生命を脅かそうとした時を描いたもの、とだけ聞きました」
ケイトは、一度息を深く吐いた。
水の妖精・ルサルカ
「私からしたら、インボルクの浄火の絵は、炎が怒り狂っているようにしか見えない。どちらも正しいかもしれないし、間違っているかもしれない」
陽気なケイトの声が一変した。
「絵は、見る人によって印象はそれぞれですから。みんながいいといえば、いいように見えてきますから」
ケイトは、ふーんと言いながらまじまじとほとりを見つめた。
「あの絵は、蒼き羽を生やした少女、水の妖精ルサルカを描いた絵。十二の精霊を従えている。水が踊っているように見えたのは、その十二の精霊だ。たぶん、だけど」
「たぶん?」
ほとりは首をかしげた。
「言い伝えで、そう言われている。そのルサルカが現れるとき、海の怒りに触れる。怒りをぶちまけるように、従えた十二の精霊が海とともに襲ってくるっていうね」
「ナイアがルサルカ。海の怒り。セリカがインボルク。炎の怒り」
「セリカ・ガルテンの創始者が世界をどう安寧に導くかを描いたとされる二枚の絵。
でも、私は災いをもたらしてはいけない戒めの絵のような気もしているんだ。浄火でだろうと海の怒りだろうと、本当のところどちらも好かない」
「どうしてそう思うんですか?」
「ルサルカはナイアとされ、実際にはもういない。そうなら十二の精霊は従えることはできず、海の怒りは起きない。
私は、インボルク派に反対する意味で、単にルサルカ派と言っているにすぎない。何かできるわけでもない。
だけど、インボルク計画は違う。インボルクの浄火を行うには、ベレノスの光という炎の力をもった石のかけらで行う。
それは実際に存在する。明日架はそれを誰よりも早く集めようと、信頼できる人を集めている。
毒されている新しい島を浄火するためと言っても、新しい島は誰もが欲しがっていて、みな、それを奪い合う。
理想水郷を作ると言っても、結局のところ争うんだよ。それで作ったものが理想水郷なのかって」
「ケイトさん……」
渚の声に力はなかった。
ここに来た理由
「こんなところに来ても同じことになるんだよ……」
ケイトは、空を見上げ、一つ息を吐いた。
「元の世界でも同じようなことを?」
ほとりが聞くと、ケイトは一瞬間を空けた。
「まぁ、そうだね。私は目の前で起きていることをただ見てるだけだったよ」
ケイトの住んでいた田舎町は、激しい対立のすえ、ダムが作られることになって、住んでいた家がダムの底になった。そこの自然が好きだった両親はショックを受けたうえ、次に住む場所選びでもめて、家庭が崩壊した。
ケイトは、底に沈んだ家の水面を眺めていた時、水面から放たれた光に飲み込まれて、セリカ・ガルテンに来た。
それを聞いたほとりは、自分と比較せずにはいられず、胸が押しつぶされそうになり、痛くなった。
「ほとり、そんな暗い顔をしないで。ほとりだって、水に苦しんでいるでしょ」
「え、どうして」
ほとりは顔を上げた。
「ここにいるみんな、水に関わるつらい出来事を経験している人しかいない」
「そうだったんですね」
「それなのに、また水と向き合わせるなんてひどい仕打ちだと思わない?」
ほとりは、まだ答えようがなく黙っていた。
理想への迷い
「でもさ、それぞれ経験したものを乗り越えて、みんなで理想水郷が作れたらいいと思ってたんだけど」
ほとりは、ケイトがそこで言葉を止めた理由がわかった。
――理想水郷を作るのに争いたくないんだ。
そして、どうしてセリカ・ガルテンに連れて来られたかもわかった。しかし、先に来たケイトが理想水郷を作ることに考えあぐねているのを見たほとりは、自分が何をすべきか、わかるはずがなかった。
――ただ、明日架さんの言うとおりしていればいいのか。
「インボルクの浄火は、大地を自然に還すことができる神の力も含まれているみたいだし、それも怖いと私は思ってる」
「それって」
ケイトは、ゆっくり頷いた。
「ウトピアクアの一つに、砂漠のピラミッド島というところがあるんだけど――」
いなきり風が、上空から吹き降りてきた。
「こんなところで光源の虫の鑑賞会ですか?」
二人の目の前に降りてきたのは、ツバメだった。小川向こうで光っていた緑の宇宙は消えて暗くなっていた。
陰った表情のツバメの声でほとりは、胸が重くなった。
地獄耳なやつ、とケイトは小声で呟いたのをほとりは聞いた。
「そうだよ。静かでいい場所だから、案内したんだ」
ケイトは、取り繕うことなく気さくに答えていた。
「あなた方は、会長との関係が深いので、強く言うつもりはありませんが、お互いあまりお近づきにならないのほうが身のためですよ」
「あぁ、気をつけるよ」
「消灯時間も迫ってきています。ほとりさん、寮に戻りますよ」
ツバメが近づいてきた。
「それじゃ、戻ろうか、ほとり。ちゃんと私が寮まで連れて行くから」
すぐにケイトがほとりを抱きかかえた。
地上で追いかけてくる二つの白い蝶の影を見ながら、ほとりは自分から動ける状態になろうと決めた。
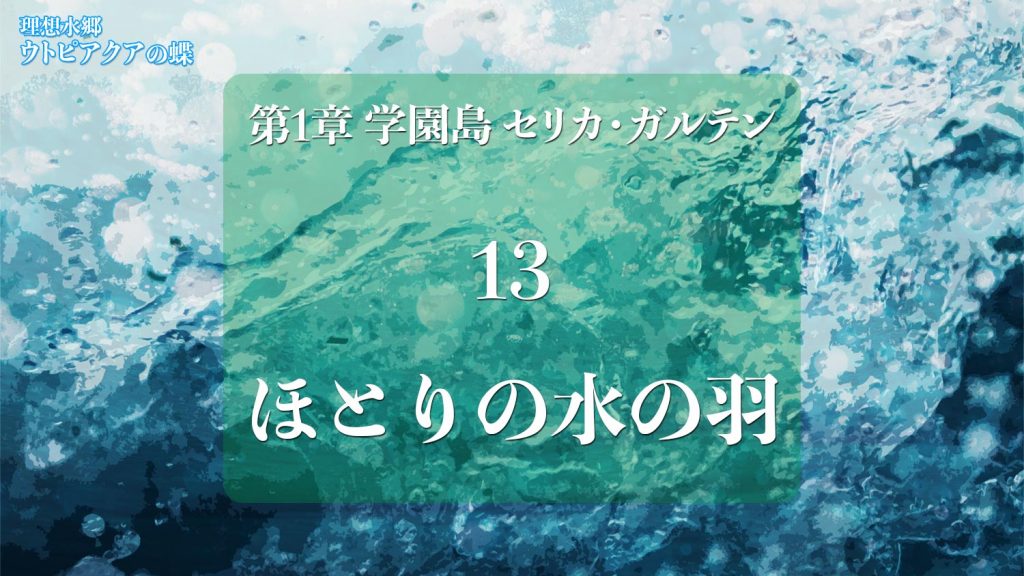
1-13.ほとりの水の羽
更新のお知らせを受けとる
SNSをフォローしていただくと、小説の更新情報を受けとることができます。


