当ブログは「note」に移行します。
新しい投稿は「note」にアップしています。
フォロー、ブックマーク、RSSでの登録、よろしいお願いします!
4-2.地底の蝶人 [小説 理想水郷ウトピアクアの蝶]
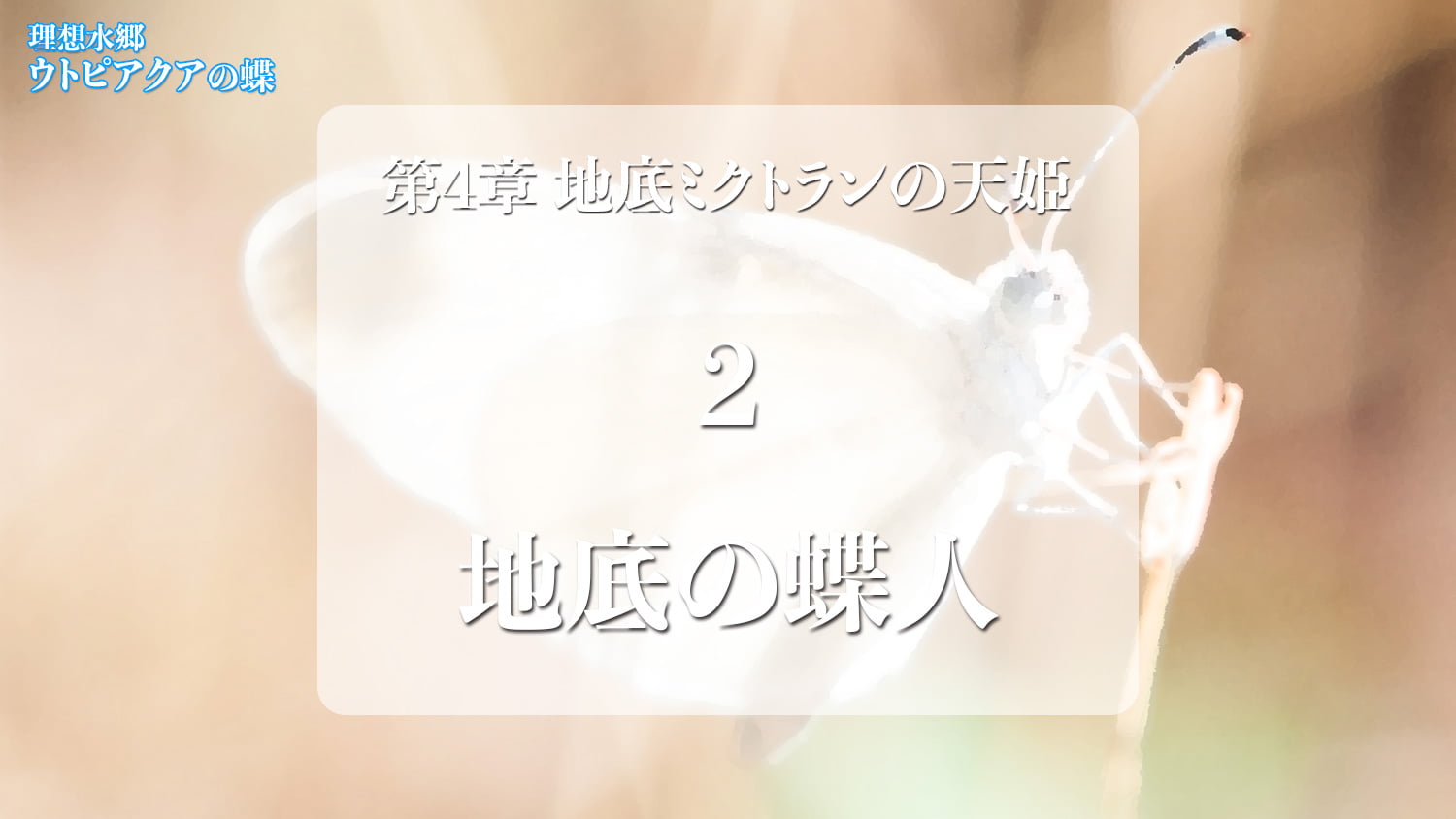
ナイア像の手には、ベレノスの光があった。それはナイアの怒りが閉じ込められていた。
そして、
インボルクの浄火の真実
ナイアのクリスタル像は、左手の手の平を上に向けている。
その手の上で、六角柱のクリスタルが光を放ちながらゆっくりと回転していた。
それを見たほとりは、それと同じ形の物が、死する前のミズホの胸にあったことを思い出した。ただ、ミズホのそれは、目の前にある物よりも小さかった。
「地上の蝶人よ。もう気づいてはおろうが、あれがベレノスの光だ。ナイアの怒りが火となって、閉じ込められている」
アダマースが言った。
よく見ると、クリスタルの中で炎が揺らいでいた。
「え――インボルクの浄火は――ナイアの怒りの――火なんですか……」
一言ずつ言い進めるほとりは、自分が何を言っているのかわからなくなっていった。
「あぁ、そうだよ。インボルクの浄火は、地上から落とされたナイアと、我々の地底人類による地上への復讐だ。
君も見たのだろ、ベレノスの光の力を」
「はい」
「そして、ベレノスの光を使った者の最後も」
「はい……」
ほとりは視線を落とした。
――それが、地上への復讐。インボルク派とルサルカ派と分けていたのは、なんだったの。
クリスタルの床にしっかりと焦点を合わせれば、沈んだ表情をする自分の顔さえ見えるほどだった。
しかし、疑問が浮かんだほとりは、顔を上げた。
「なぜ、地底にあるベレノスの光が、地上に?」
ほとりが聞くと、アダマースが向き直った。
「
クォーツ、君のも見せてやりなさい」
「はい」
目を閉じたクォーツは、アダマースに軽く頭を下げた。すると、クォーツの背中に、真っ白な蝶の羽が出現した。
ほとりは、目を丸くし、羽の生えた少女とだけ理解して、頭の中が真っ白になり、意識を失った。
地底に来てから、地上では考えもしなかったことが起こり、ほとりの思考の限界を越えてしまっていた。
クォーツ・ロック
ほとりが目を開けると、白い天井が目に入った。
「あれ、私……」
ほとりは額に手を当てた。ほとりは、寝台に寝かされていた。
「目が覚めましたか」
背中を向けていたラーワが、部屋の隅から近づいてきた。
「だいぶお疲れのようで、このままここでゆっくりしていってください。
もし、ご用がありましたら、外を通るものに声をかけてください。では」
ラーワは部屋を出て行った。ほとりは、辺りを見回した。
小さな机の上にガラスの瓶が立っていた。
「あっ」
ほとりは慌てて起き上がり、机の上の瓶を手に取った。ほとりの唯一の持ち物、肩に掛けていた水筒だ。
それを胸に押し当てて、目を閉じた。次に目を開けたら、祖母の小屋の中に戻ってと願った。
そっと目を開けると、その願いはどこにも届いてはいなかった。
ガラス瓶の水筒が、いつもより輝いているように見えると思った時、声がした。
「目、覚めた? 大丈夫?」
窓の外、ガラスのように遮るものはなく、そのまま外に出れるようになっていた。そこに羽を生やしたクォーツが立っていた。
先の白装束とは違う白い羽織を身にまとっていた。
「クォーツさん」
「クォーツ・ロック。クォーツでいいよ。ほとりだっけ」
「はい」
「ね、地上の話を聞かせて」
アダマースやラーワといた時とは違って、目を輝かせて笑顔だった。
「クォーツ、いえ天姫様。勝手に神殿に入られては困ります」
窓の外から声が聞こえてきた。ほとりは窓に近づき、外を見ると、階の建物の上にいることがわかった。
「もううるさいな。静かなところで話を聞かせてくれない?」
クォーツに爛々と見つめられたが、ほとりは悪い印象を抱かなかった。むしろ、聞きたいこともあったから都合がいいと思って、頷いた。
「さ、行こう。いろいろ地上のこと聞きたくってさ。地上には、テンキというものがあるんでしょ? 水を降らせたり、光が熱かったり」
ほとりは手を握られて、クォーツに勢いよく引っぱられた。
「待って。私、羽はあるけど、飛べなくて」
「あ、そうだったね」
地底の町
クォーツは、思いの外慣れたようにほとりを抱えて、部屋から飛び上がった。
神殿の外を見張っていた男たちの声はすぐに聞こえなくなり、地底空間に広がる町並に視界を奪われた。
そこは、ぽっかりと空いた大きな空間だった。神殿は高い丘の上にあり、白い世界が広がっていた。
家の屋根も壁も道も白かった。
しかし、天井だけは土がむき出しだった。それを支えるかのような太い柱が何本も立っていて、それらはクリスタルの柱で、地底空間を照らしていた。
「ここは、ミクトラン光帝のお膝元プロフォンドムという町。
ミクトランは、三つの大きな街に分かれているの。左右に見える大きな岩壁の先にも町がある」
扉が半分開けられているように、地面と天井がつながった大きな壁で、区域が分けられていた。
人としての繁殖が確実にあり、町を人々が行き交っていたが、飛んでいる者はクォーツとほとりだけだった。
子供たちが笑顔で手を振っていた。
クォーツが手を振ってあげてと言うので振ると、子供たちはさらに笑顔を返してくれた。
ほとりは、人々を見る限り幸せのように思えた。しかし、茶色い天井に閉じ込められたここが息苦しくも感じた。
――ここから地上に戻る手段はないのか。戻りたい。
クォーツに連れてきてもらった場所は、ちょうど神殿の真向かいに当たる高い岩壁の上だった。
洞窟の入り口が静かに口を開けていた。入り口の周囲から中へ向かって、小さなクリスタルが苔のように生えている。
「ここは」
ほとりが聞いた。
「クリスタルの廃坑。ここにいくつもこういう穴があるの」
クォーツは、洞窟の中へ入っていった。ほとりもあとを着いて穴の中へ入っていく。
クリスタルが道案内をするかのように、奥へ向かって光が流れていった。
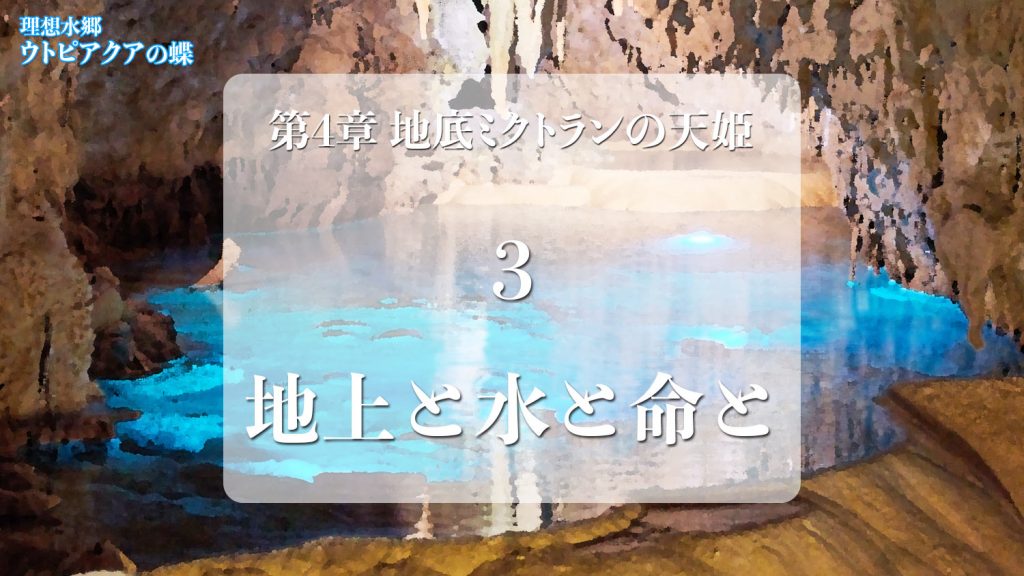
4-3.地上と水と命と


