当ブログは「note」に移行します。
新しい投稿は「note」にアップしています。
フォロー、ブックマーク、RSSでの登録、よろしいお願いします!
2-8.脱出の一人劇 [小説 理想水郷ウトピアクアの蝶]

ただただ水を瓶に入れる作業がほとりの思考を奪っていく。
ほとりは不安を抱きながら寝る時間に脱出方法を思いつく。飛べない羽を持つほとりは、翌日の作業中にひと芝居うつ。
水があること
休憩時間を告げられると、また空き瓶に水を入れるだけの単純作業が始まった。
汚れた川、濁った水、異臭が頭に蘇るも、それは想像だったかのように、たちまち思い出せなくなる。
当たり前のように蛇口をひねると、水が出てくる。出てこないことなど、想像できず、安心感が薄れていく。
――あんな町で水に飢えるより、ここにいた方が……。
ほとりは、いやいやと首を振った。
作業に慣れると、次々と空き瓶の入ったケースが運ばれてきて、ほとりは無心で作業していたことに気づいた。
わずかな食事の量と時間を与えられ、寝ることも、列ごと順番に行われた。そして、どの部屋も窓がなく、外の時間がまったくわからなかった。
大部屋で雑魚寝を強いられていて、誰も文句を言わず、薄明かりが消えると、意識も消されたように寝息に包まれる。
脱出案
疲れていたほとりだったが、この生活が一生続くことを考えると、不安で押しつぶされそうになり、眠れなかった。
しかし、そこに唯一の自分がいた。
――こんなウトピアクアは、嫌だ。
いつか、この島も理想水郷の名にふさわしいものにしたいと、強く思ったほとりは、まずここから逃げ出そうと考え始めた。
各出入り口には監守が立ち、作業中も巡回に来る。隙を見つけて逃げるのは難しかった。
たとえ、上手く施設から外に出られたとしても周囲は森。トラックが通ってきた道を使っても、見つかれば捕まってしまう。
川があるとはいえ、汚染された水では飲むことができず、歩き続けることもできない。
蝶の羽があるのに、飛べないことを悔やむほとりだったが、そこで唯一安全にここを出る方法が思い浮かんだ。
ただ、出た後のことを考えると、さらに不安が募るばかり。
しかし、ついに不安が睡魔に負け、ほとりは眠ってしまった。
決行へ
監守に起こされたほとりの頭は、重かった。
寝ている際も、飛ぶ練習をし、何度も崖から落ちる夢を見ていた。
ちょっとの食事を終えた後、また水を瓶に入れる作業が始まった。
ほとりの呼吸は、早かった。思いついた脱出案をいつ実行するか、周囲を見渡しながら、作業を進める。
作業場には、昨日にはないただならぬ緊張感があった。
監守の数が、なぜか、昨日に比べると多く、作業員一人一人を鋭い目つきで、確認しているようだった。
あからさまに、ほとりもじろじろと見られていた。
「そっちはどうだ?」
監守同士が声をかけ合っていた。
「わかるわけないだろ。急に見つけ出せって言われても、名簿すら作ってるわけじゃないから」
「そうだな。ここにぶち込んだら、もう外に出すことないからな。とにかく、特徴のあるやつを見つけ出せ」
監守は、焦り気味にまた見回り始めた。
ほとりの手は、水に濡れているのに、瓶を持つ手が汗ばんでいるように感じられた。
監守が多かろうが、周囲の視線が気になろうが、脱出案の方法には変更なかったが、ほとりは、ケースに伸ばす手をなかなか止めることはできなかった。
フリークになる
十一個目のケースに手をつけなかったほとりは、震える右手をゆっくり首の裏筋へ回す。
濡れた指先が肌に触れる。
いつも以上に背中を伝う刺激が冷たかった。
まるで全身に鳥肌を立たつかのように、ほとりの体が震えた。
同時に、ほとりの背中に、透き通った水の羽が生えた。
「いやーーー」
ほとりは、叫び声を上げ、ふらふらっと通路によろめき出る。
空の瓶ケースにぶつかると、ケースがひっくり返り、空の瓶が床に勢いよく転がっていく。
いっせいに周囲の作業員の視線がほとりに向いた。
ほとりの羽を見た作業員たちは、目を丸くして、その場から逃げていく。
「おい、どうした? 持ち場につけ」
「いたぞ! フリークだ」
近くの監守が異変に近づき、いっせいに駆けつけてきた。
「本当にフリークが紛れ込んでいたのか」
「ど、どうしたら? 触れて大丈夫でしょうか……」
ほとりが戸惑う監守たちに助けを求めるように手を伸ばすと、ほとりを取り囲んでいた監守たちは、息を飲み、一歩足を引いた。
ほとりは、一歩二歩と進んでから、膝から折れるように倒れた。
そして、ほとりを覆いながら、ほとりの羽が消えた。
「おい、大丈夫か?」
工場を出る
倒れて見せたほとりは、監守がなかなか触れてこなかったため、意識を取り戻したようにゆっくり起き上がった。
騒然とする中、監守に縛られて、作業場から連れ出された。
フリークにはフリークの場所がある、とだけ言われて、工場の外に用意されたトラックの荷台に、着の身着のまま乗せられた。
すぐにトラックは動き出した。荷台を覆う布の隙間から、外を見ると、日が沈みかけていた。
町に比べると薄雲で、森が広がっていた。しかし、水汚しの施設を過ぎてから、川は濁り、木は枯れ、荒れ果てた景色に変わった。
少しずつ、鼻をつく臭いが強まり、慌てて顔を引っ込め、荷台の奥で縮こまった。
しばらく車に揺られたあと、トラックが止まった。
降りるよう指示されて、荷台から出ると、そこは、サーカスのテント小屋裏だった。
先日の夜に見たままのトレーラーハウスや檻がそこにあった。
テント小屋の裏口から中へ案内されると、薄い壁越しに音楽と歓声、拍手が聞こえてくる。
細い通路を進んで、荷物がただ置かれた小さな部屋に通されると、何も言わずにドアが閉められた。
ほとりは、閉じ込められたと思ったが、ドアに鍵はなく、出ようと思えば出られることがわかった。
部屋は物置で、窓はない。
ドアに近づくと、すぐ外で話し声が聞こえる。
「それでは、あとよろしくお願いします」
案内係の足音が遠ざかっていくのを聞いていると、ドアがゆっくり開いた。
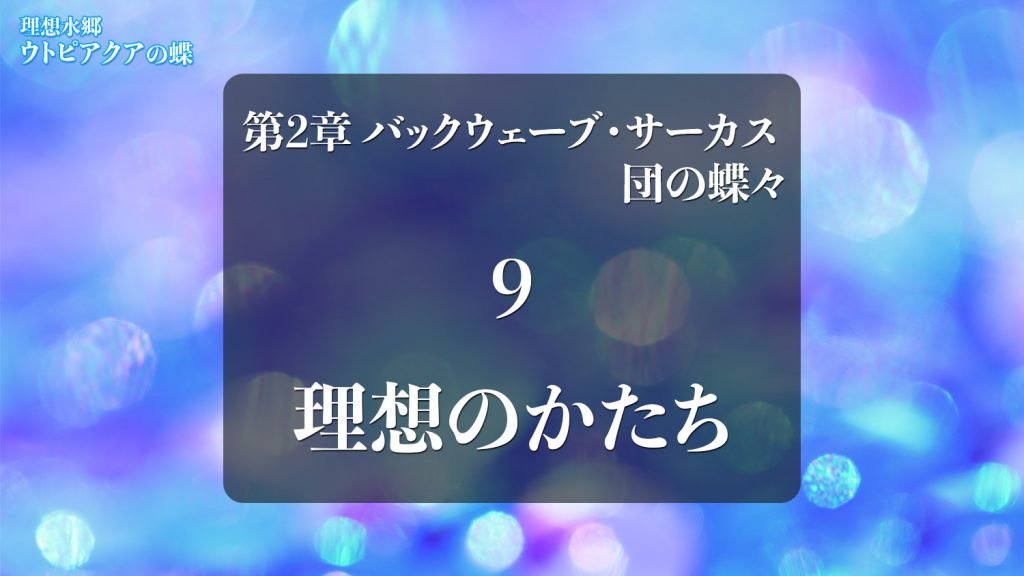
2-9.理想のかたち
更新のお知らせを受けとる
SNSをフォローしていただくと、小説の更新情報を受けとることができます。


