当ブログは「note」に移行します。
新しい投稿は「note」にアップしています。
フォロー、ブックマーク、RSSでの登録、よろしいお願いします!
1-11.夜の光 [小説 理想水郷ウトピアクアの蝶]

連れて行きたい場所があると、ほとりはケイトに抱えられて飛ぶ。地面に映る夜の影は白いことに気づく。
そして、奥園でケイトに渡された物は、納屋にあったガラスの瓶だった。
白い影
雲一つない星空の夜。月も無数の星々とそこに同居していた。
ほとりは、初めてといっていいほど、絵に描いた夜空を見た。星が落ちてくる錯覚を感じるほど、圧迫感があった。
もとの世界にいたら見ることなかったと、ほとりは思った。
待っていたケイトは、せっかくだから夜にしか見れない光景がある奥園に案内すると言って、ほとりを背後から抱きしめるように抱えて飛んだ。
夜の空中散歩以上の光景が、いったいどこにあるというのだろうか。
ケイトの飛行は、明日架の時より優しく、ゆっくりで、高くもない。ほとりは、地面に近い方が怖いようにも感じられた。
月の照らされて二人の影が、真下の地面を、時には庭木の上を一緒に移動していた。その影は、太陽光の時とは違って柔らかく、そして白かった。
何度見返しても地上に落ちる影は、心を空かしているかのように、白く光って見えた。
ほとりは首を回してケイトを見上げる。しかし、ケイトの顔にかかる影は黒かった。そのせいか、飛ぶことに必死さが感じられた。
ケイトの羽は、明日架より一回り小さかった。その分、飛翔する力は少なく、人一人抱えて飛ぶのが限界のようだった。
「怖い? もうすぐだから」
ケイトが笑顔を見せて言った。
「あ、はい。あの」
「なに?」
「ここって、影は、白いんですか?」
妖精の影
「もう気づいたんだ。ほとりは、観察力あるね」
ケイトは、ここに来てからしばらく気づかなかったと言う。他の生徒が夜、自分の影が白いことに悲鳴を上げて騒ぎになって、知ったらしかった。
「いちよう月と呼んでるあれの光を浴びた私たちの影は、ここではなぜか白い。でも、白い影は地上にしか出ない」
「どうしてですか?」
ほとりは、反射的に聞いてしまった。
「私たちが
「蝶人……本当に妖精になっちゃったんだ」
「そうだよ。羽が生えて、空を飛んで、月の光の影は白かったんだ、妖精は」
子供の頃読んだ本に、妖精の影について思い返してみたが、思い当たらなかった。
「さ、着くよ」
ケイトは、高度を下げていく。予想着地点を見定めると、明かりはなく、小川が月明かりを静かに反射していた。
忘れ物
ケイトに連れてこられた奥園は、手入れが行き届いた背の高い木や苔が広がる落ち着いた庭園だった。
寮の前に比べると、風に水分が含まれ、土や葉の匂いも強かった。
まだ奥に続く道から一段下がった小川の前に石を四角く切り出しただけのベンチがあった。ケイトは、腰かけて一息ついた。
「ありがとうございます。疲れていませんか?」
「大丈夫大丈夫。ほとりも座りなよ」
ほとりは座ると、石に熱をもっていかれると同時に、静寂に包まれた。すぐに、静寂は辺りの自然の騒がしさに飲み込まれて、うるさくなった。
まるで、自然がにぎやかに活動しているように感じられた。
「はい、これ、渡したいもの。ほとり、忘れていったでしょ」
ケイトが肩からにかけていた紐を外して、差し出した。それは、納屋にあったガラスの瓶だった。厚めの布で仕立てられたショルダーケースに入れられていた。
「ケースは、私が以前使っていたやつだけど、よかったら使ってやって」
「この瓶、どこで?」
「私たちのいけすに浮いていたのを見つけた。ほとりが一緒に持ってきた物じゃないの?」
ほとりは、納屋でその瓶が光り出したところまでは記憶しているが、そのあと空から落ちている間、その瓶をどうしていたか覚えていない。それどころではなかった。
「私のというより、おばあちゃんちにあったものなんです。これを見つけた瞬間に光に飲み込まれて」
ほとりがそれを首にかけた。それにしても瓶を入れる布のケースがぴったりのサイズだった。
「おばあちゃんの大事なものだったのかな」
ケイトが聞いてきた。
「物置小屋にあったものだから、そういうものじゃないような気もします」
「でも、すごいきれいなガラス瓶だよ。ほとりは、それを水筒代わりにしなよ。あとで、水筒もらえるとは思うけど」
「水筒?」
「そう。学舎から離れるときは、携帯することになってる。ここも、どこでも水が飲めるわけじゃないから。食堂で頼めば、入れてもらえる」
ほとりは、コンコンと指で軽く叩いてみた。厚みのある瓶ではなかったが、とても硬いように感じられた。肩紐のついたケースに入れておけば、落ちることはなさそうだった。
奥園の光源
「しっ!」
ケイトが唇に人差し指を立てた。小川の向こうの茂みをじっと見つめていた。
ほとりは、獣がいるのか、それとも聞いてはいけない声の主がそこにいるのかという恐怖で背筋が凍り、そっとケイトに体を寄り添わせた。
跳ね上がった鼓動が一番うるさく、水分を含んだ風が、気持ち悪く感じる。
茂みの一点が、緑色に灯った。
じんわり小さな光が強くなり、弱まる。
それは、一点だけでなく、だんだんと数が増えていった。
そのうち、一点が浮遊して、緑色の線を宙に描いた。
「蛍」
ほとりは、小声で言った。
「ほたる?」
「はい。こういう静かできれいな水のある場所に住んでいる虫です。尾を光らすんです」
「蛍という光る虫なのか……」
「あ、でも、元の私の住んでいた国の話で、それだと断言はできませんけど」
間違ってはいけないと、慌ててほとりはつけ加えた。
「蛍で、決定。ここでは、まだ名前がないからそれで。そっか、ほとりは蛍を知っていたのか」
ケイトは、残念そうだった。
「はい。でも、こんな数を見たのは、初めてです」
小川の向こうは、緑色の星々が輝く宇宙になっていた。
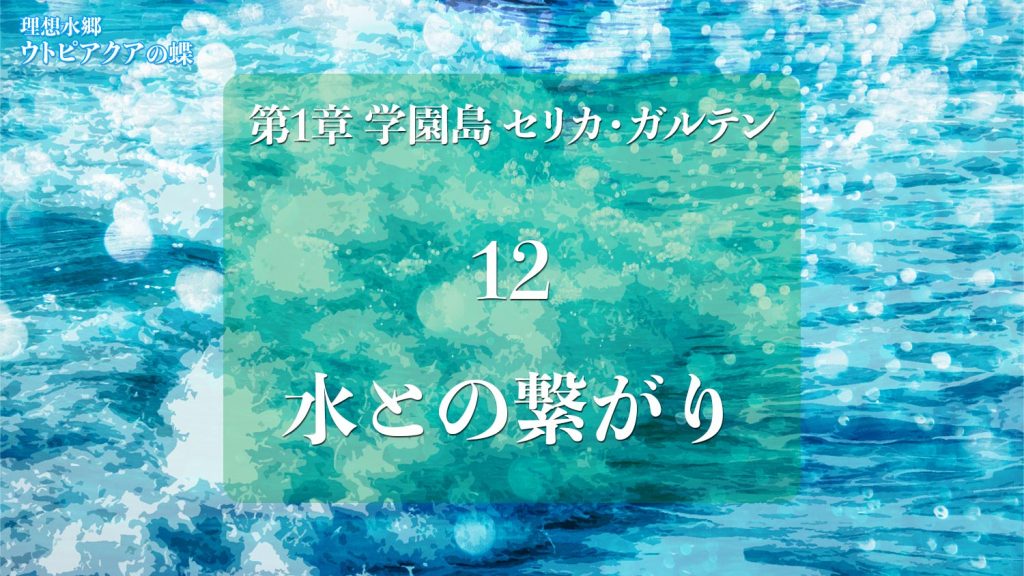
1-12.水との繋がり
更新のお知らせを受けとる
SNSをフォローしていただくと、小説の更新情報を受けとることができます。


