当ブログは「note」に移行します。
新しい投稿は「note」にアップしています。
フォロー、ブックマーク、RSSでの登録、よろしいお願いします!
3-12.黒蝶の死 [小説 理想水郷ウトピアクアの蝶]

ほとりは、炎をまとったミズホと
大腐死蝶を倒し、力尽きたミズホは、薄れていく意識の中、ほとりに予言の子の真意を伝える。そして、現れた妹の前で、命を引き取った。
小さな炎の巨人
大腐死蝶が、前方に向けて羽を一振りした。
突風にあおられたミズホがまとう炎は、なびいて火種のように小さくなっていく。
風に耐えるも、炎が消える。
次の瞬間、どこに隠されていたのかと思うほどの炎が上がる。それは、巨人を模した炎だった。
大腐死蝶の半分ほどの大きさで、巨人は大腐死蝶を正面から体をぶつけて食い止める。
巨体同士の激突から生まれた衝撃波が空間を走った。
「私は、いったい何を見ているの?」
ほとりは、鳥肌が立って震える体を押さえ込んで言った。
「たぶん、これがインボルクの浄火。規模の小さいな初期段階」
取っ組み合っている二つの巨体を、隣で目を細めて見ていたユーリが言った。
炎の巨人は、大腐死蝶に押されている。
ほとりは、ふと、明日架の存在を探すと、上空で、同じようにその戦いを見ていた。
その表情は、笑っているように見えた。
遠くて、気のせいだったかもしれない。
次々とデフトたちが、大腐死蝶に飛び込んでいき、融合していく。
ボロボロだった大腐死蝶の羽が、穴のない羽となった。
一度羽ばたかせるだけで、巨体が浮かび上がる。
つかまれている炎の巨人も浮いた。
真っ白な一直線の光が、大腐死蝶を貫いた。炎の巨人から放たれたその光は、片方の羽を切り落として消えた。
羽が切り落とされた大腐死蝶の背中からは、炎が上がっている。
切られた羽の切り口からも炎が、全体に延焼していき、バラバラと黒い小さなものが降っていく。それは、融合していたデフトだった。
炎の巨人は、形を失い、単なる炎へと姿が元に戻ってしまった。
片羽を失って体のバランスを失う大腐死蝶の周囲を、ミズホは、龍のように炎を伸ばしてぐるぐると回る。
そして、大腐死蝶の体の中に突っ込んで、貫通する。まるで、糸で縫うようにして、大腐死蝶の体に出たり入ったりを何度も繰り返した。
ハエを払うかのような大腐死蝶の動きをかわして、ミズホは大腐死蝶の中に入ったままで出てこなくなってしまった。
大腐死蝶も炎の先頭が見つからず、動きを止めた。
「くっ」
ほとりは、腕で目を覆った。
大腐死蝶に空いた穴という穴から、一気に光が放出され、辺り一帯に光が拡散した。
そして、それは爆発した。青い空に真っ黒な煙を昇らせて。
予言の子・ルサルカ
ほとりは、ユーリを水の羽で包み、事なきを得た。
「ユーリ、大丈夫?」
「あぁ、ほとり、ありがとう」
上空にいた蝶人たちやデフトは、大腐死蝶の爆風で吹き飛ばされてしまっていた。
大きな黒煙が天に昇っていく場所から、小さな光が落ちていくのを見たほとりは、明日架やララたちことが心配だったが、ユーリに光の落ちた場所に連れて行ってもらう。
大腐死蝶の爆発で、いくつもあった砂漠の丘はなくなり、隕石でも落ちたかのような跡ができていた。
その中心に倒れていた黒焦げたミズホのもとにやってきたほとりとユーリ。
「ミズホさん」
ほとりの問いかけに弱々しく目を開けた。体から煙りを上げる彼女の胸元には、まだ光り輝く小さな石があった。
「ほとり……最後に……会えてよかった……」
「ミズホさん。すぐに手当を……」
「いや、いいんだ。それより、ほとり。やっぱり、君は予言の子だ」
「あとで、聞きますから。ユーリ、ミズホさんを運んで」
ほとりは、ミズホに力なく手をつかまれた。
「ほとり。君は、ルサルカの力を持っている。ほとりの水の羽には、浄水の力がある」
ルサルカは、インボルクの浄火とは反対に、暴れる水ことだと思っていた。
ほとりは、そして、ユーリもミズホの言っていることが、すぐには理解できなかった。
ほとりの羽をかじって白い煙を上げて蒸発したデフトを見て、ミズホは確信していた。毒された体のデフトが、ルサルカの力を含んだ水によって清められた、と説明した。
もし、ミズホの言うように、ルサルカの力を持つ者の意味として、予言の子というのであれば、なぜ、明日架はそんなほとりをインボルク計画に引き入れているのか疑問が浮かぶ。
「インボルクもルサルカも使い方しだいだ。私のようなひどい使い方をしないでほしい」
ほとりとミズホは、静かに見つめ合った。
姉の死
「ミズホさん――」
「姉さん――」
ほとりは、ツバメの声を聞き間違うことはなかった。
マノンとツバメが同時に降り立ち、マノンはほとりの反対側に回り、膝を砂に埋めた。二人とも、ミズホの姿に言葉を失っていた。
「マノン、ほとりを助けてあげなさい」
マノンは小さく頷くだけだった。
「頑張ってるようね、ツバメ」
ミズホは、ゆっくりと頭上に立ち尽くしたままのツバメに視線を動かした。
ツバメは、普段と変わらず、表情を変えない。しかし、ミズホの表情は、マノンや私に見せるそれとは違い、いつになく柔らかいものだった。
「私のように、理想水郷を作らないでね。ツバメならいいウトピアクアを作れるから、頑張ってね」
ミズホは、笑顔を見せ、目を閉じた。
二度と、その目が開くことはないと、ミズホの手を握っていたほとりにはわかった。ミズホの手から、一切の力がなくなり、ただ、熱と重さだけが残っていた。
「ほとり、こっちに来ていたのか……良かった」
明日架が、ララとケイトともにやってきた。
「ミズホ……。明日架、これでもインボルク計画を?」
ケイトが言う。
「えぇ。失敗はしない。良くも悪くも彼女が手本を見せてくれた」
「明日架、ツバメの前で」
「いいんです、これで。姉さんは姉さんなりに、この島を正そうとしたんだと思います。
結果的に、私たちにもいろいろと教訓を残してくれました。失敗を学び、活かしていくのが残された私たちの役目です」
たんたんと答えたツバメだった。
「あんた……」
「黒スカーフは、死しても黒いまま……か。これは――」
明日架がミズホの胸元で光る石に手を伸ばした時だった。
ミズホの黒いスカーフが突然一人でに広がって、ミズホの体を包み込み始めた。明日架は、慌てて手を引っ込めた。
ミズホの遺体は、黒スカーフに包み込まれ、まるでブラックホールが閉じるかのようにスカーフが収縮し、目の前からミズホの体もろともなくなってしまった。
「黒スカーフは、体の情報を残さないためのものだったのか。最後は、存在をも消してしまう……か」
明日架は、立ち上がって人型の砂後に静かに視線を落とした。
「死んだら何にも残らない。自分の爪は、最後まで生きて残す」
そうつぶやいたツバメの足下に落ちた水滴は、またたく間に砂漠に吸収されて、乾いていった。
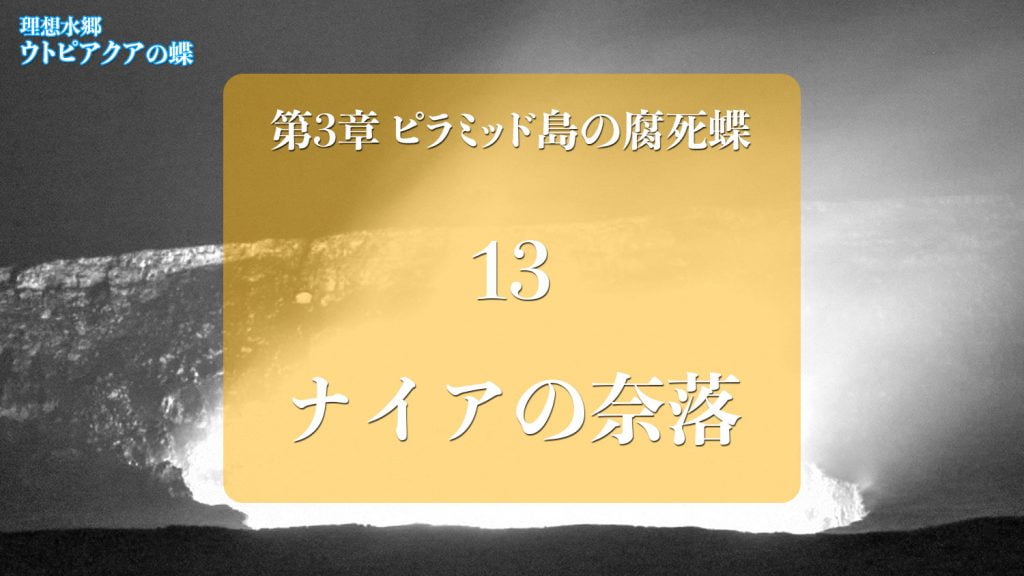
3-13.ナイアの奈落


