当ブログは「note」に移行します。
新しい投稿は「note」にアップしています。
フォロー、ブックマーク、RSSでの登録、よろしいお願いします!
6-2.ベレノスの光 [小説 理想水郷ウトピアクアの蝶]
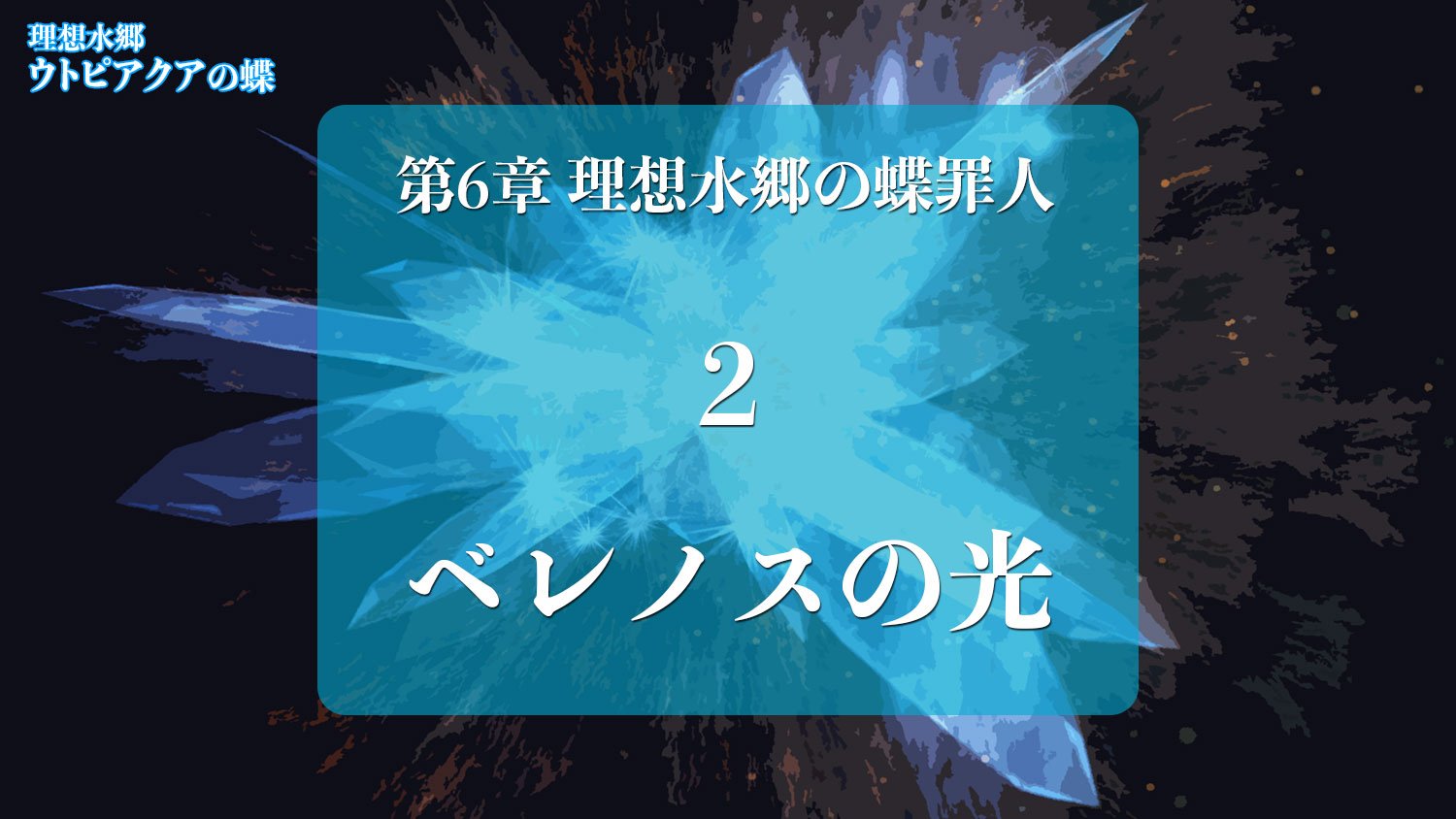
ほとりとクォーツが移動した場所は、ベレノスの光が現れる山だった。
ほとりは、ツバメにベレノスの光を奪われ、崖から突き落とされてしまう。
理想の相違
ツバメの背後に立つ黒い山が、ツバメの心を反映しているようにしか、ほとりには見えなかった。
「セリカ・ガルテンに誰もいませんでしたが、みんなは……それにここはいったい」
ほとりは、意を決して聞いた。
「あのセリカ・ガルテンは、もういらない。腐死蝶は殺しても殺しても学園に湧いてくる。
今、会長をはじめ、みんなでベレノスの光を山頂に取りに行っている。他の島の蝶人どももいるから、人数が必要なの」
ほとりとクォーツは、塔のように伸びる黒い山の上を見上げた。どこが山頂なのか霞んでいてよくわからない。
ベレノスの光が山の上にあるのか不思議だと思った。しかし、地底で水が放出されていたことと、ベレノスの光を祭壇の上に置いておくことから推察すれば、地底と山頂がつながっていて、水が山頂まで運ぶこと以外考えられない。
「もちろん、会長がベレノスの光を手に入れて、新しい島をウトピアクアにし、セリカ・ガルテンとしても作り直す。
そう。これから邪魔者は、島とともにインボルクの浄火で、焼き払うのよ」
依然と淡々と語るツバメの発言が、冗談とは思えず、むしろ恐怖すらほとりには感じられた。
「インボルクの浄火は、大地を焼き尽くして、奪い取るためのものではありません。
みんなの祈りを天へ届けるためのものなんです。理想への誓い、象徴なんです。私は、それを明日架さんに伝えたい」
ほとりはベレノスの光を強く抱えたまま言った。
「まるで使い方を知ったような口ぶりね」
脳裏に炎に包まれたミズホの姿が浮かび上がる。それはツバメも同じだった。しかし、ほとりは、大樹王が燃える光景を強く抱いていた。
蝶人ツバメ
「もしかして、あなたが抱えているものは、ベレノスの光?」
ほとりの抱える腕に、無意識に力が入った。
「あなた、どこでそれを手に入れたの?」
「そんなこと、どこだっていいでしょ」
羽を広げたクォーツがクリスタルの剣を体の前で構えた。
「ふふ、ベレノスの光がもう一つあるなら、それにこしたことはない。
よくやったわ、ほとり。それをよこしなさい。私が、会長に届けるわ」
「なんで、あなたに渡す必要がある」
「ほとりが連れてくる蝶人は、うるさいやつらばかりね」
ツバメは、すっと手をクォーツに向けた。また蝶がどこからともなく現れた。
「な、なに、なに」
クォーツの持つ剣に蝶が山のように集まり、クォーツは振り払おうとするも、あっという間に剣が見えなくなってましった。
「あっ」
クォーツが握っていた剣は消え、一瞬でツバメの手に移動してしまった。
ほとりは、その光景を見て、ツバメが再三自分の前によく現れるのを思い出した。裏山にいた時、ケイトと川辺で蛍を見ながら話していた時も。すべては、蝶から情報を得てツバメに監視されていた。
「それをよこしなさい」
クォーツがツバメの前に立ちはだかる。
「クォーツ……」
「状況が全然わからないけど、私はほとりの見方だから」
「あなたが守る対象は、もう消えた存在なの。ここにいられては困るのよっ」
ツバメは、剣を振り降ろす。
クォーツは、からがら横へ避けた。
「ほとりと一緒に飛んで逃げる手もあったのに」
あっ、と、虚をつかれた表情をしているクォーツに、ツバメが手をかざすと、大群の蝶がクォーツを集まりだした。
顔だけが見える状態で、クォーツはまるで蝶の重さに耐えられないかのように、その場に倒れ込んでしまった。
「飛べないあなたは、本当に用済みなのよ」
ツバメとの距離を保つようにほとりは、一歩一歩下がっていく。しかし、崖から吹き上げる風がほとりの背中を押し止めた。
ほとりは、また一か八か飛び降りて、飛べるか試そうか考えた。しかし、飛べればいいが、飛べなければ落ちて、どうしたらいいのか何も考えられずにいると、ツバメがまた剣を振り降ろしてきた。
剣先とベレノスの光がぶつかって、甲高い音と同時に、腕に衝撃が走り、ほとりは抱えていたベレノスの光を落としてしまった。
崖の縁、ぎりぎりでベレノスの光はとどまった。
その時、山の上から歓声が聞こえてきた。
そして、噴火でもしたのかのように山頂が赤く染まる。
「ついに手にしたようね」
ツバメの口ぶりから、明日架もしくは別の誰かがベレノスの光を手にし、それを使ったのだろう。
たちどころに、いくつもの炎が上がり始め、それらがいっせいに、月の下を通って、どこかへ飛んでいく。
まるで、巣立ちをしていく不死鳥のように、炎の羽を広げ、尾を伸ばし、同じ方向に飛んでいった。
決別
「どうしてあんなに……」
ほとりは空を見上げたまま言った。
「ベレノスの光を一人で使えば、体に与える影響は大きい。姉さんの一件でよくわかった。
会長は、ベレノスの光を細かく分けて、多くの者とインボルクの浄火を行うことにした」
ツバメが答えた。ほとりは、それで明日架が派閥を作ってでも、人を集めていた理由がわかった。
「新しい島は、思ったよりも大きくて人手が必要。もう一つ、ベレノスの光が手には入って良かった。
二度と、私と会長の前に現れないで」
「私は別に……ただ理想水郷をみんなで作れれば――ッ」
ツバメは、一歩ほとりに近づいた。
ほとりは、にぶい衝撃の一瞬あとに、腹部に痛みを通り越す冷たい氷を差し込まれたように、全身が冷たくなった。
「ほとりっ」
クォーツの声で、我に返ったほとりは、視線を下げた。
ツバメが握るクリスタルの剣が、自分の腹部に突き刺さっていた。
「私が会長とともに生きるのよ」
ほとりは、見たままの状況は理解できていた。だが、そこから思考は進まず、表情のないツバメをただ見つめることしかできなかった。
「ツバメ、そこで何をしている」
ケイトの声だった。三人の蝶人が、黒い山肌を滑空してきた。
「もう遅い。予言の子、さようなら」
剣をほとりの腹部から引き抜くと、ほとりは力なく、そのまま後ろへひっくり返って崖から落ちていく。
「ほとり――」
クォーツの叫び声が聞こえた。一瞬、声の方を見ると、飛んでくるケイト、ユーリ、ララの姿が見えた。
しかし、崖の荒い表面が逆さまに流れてきて、三人の姿を見えなくした。
「ほとり――」
「ほとりさーん」
ユーリとララが崖を飛び出し、真っ逆さまに追いかけてくる。
手を伸ばしてくるも、ほとりはそれをつかむことはできず、そのまま海に落ちてしまった。
無数の泡に包まれたほとりは、力なく闇の中へ吸い込まれるように沈んでいく。
ユーリかララが、潜って来ようとしていたが、激しい波でその姿はもみ消され、ほとりは意識を失った。
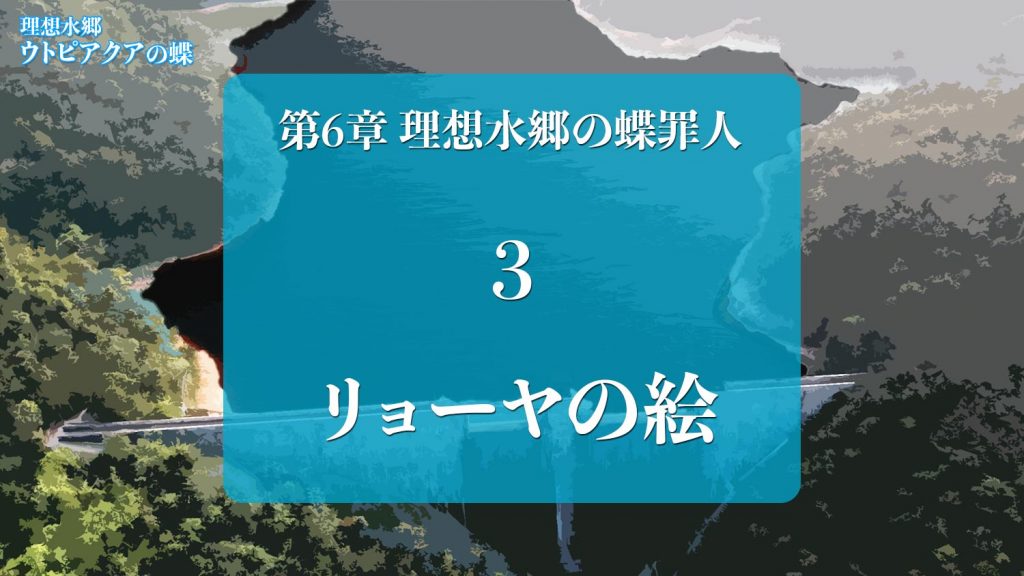
6-3.リョーヤの絵


