当ブログは「note」に移行します。
新しい投稿は「note」にアップしています。
フォロー、ブックマーク、RSSでの登録、よろしいお願いします!
6-1.蝶人ふたたび [小説 理想水郷ウトピアクアの蝶]
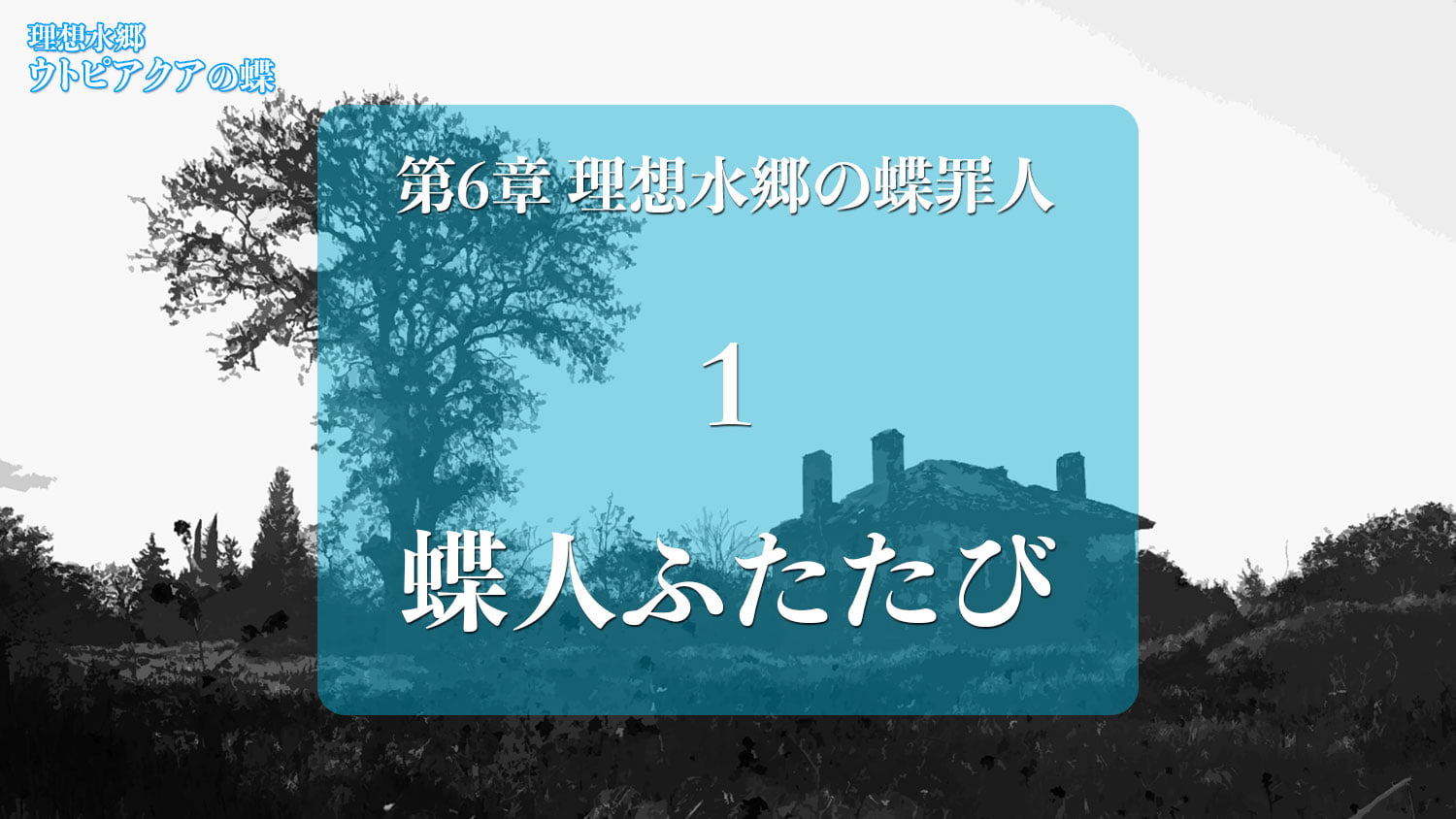
ほとりとクォーツがセリカ・ガルテンに戻ると、そこには誰もいなかった。
庭を荒らし、住み着いた
あり続ける青
異様な静けさの裏山をほとりとクォーツは降りていく。
「さっきのところよりは、過ごしやすいよ、ここ。それに、すごい静かなところね」
後ろについて、すっかり顔色のよくなったクォーツが言った。
「そう、良かった。確かに静かなところだけど、今日は静かすぎるくらい」
山道を出て、寮と学舎の間を通って表側に回ろうとした時だった。
「ほとりっ! 肩に、私たちと同じ羽の――」
クォーツがおっかなびっくり声を上げた。
ほとりが自分の肩に目をやると、蝶が一匹とまっていた。
「蝶っていう生き物。地上には、こういった羽のついたいろんな生き物がいっぱいいるよ」
――この蝶、どこかで。
いつだったか、食堂で食事をしている時に目の前を飛んでいたことを思い出した。
ほとりはその蝶を気にすることなく進んで、寮の建物の前に出た。
丘上から見える地上の光景をクォーツに堂々見せる気まんまんでいたほとりだったが、変わり果てた光景に言葉を失った。
きれいに手入れが行き届いていたはずの花や木々が植えられた庭が、見るも無惨にボロボロにされていた。
手入れが放置されているだけでなく、何者かに破壊されているようにも見えた。
「一体、なにが……」
やっと出てきた言葉の答えを探すも見つからない。
「クォーツ……本当はもっともっときれいな庭なの。どうしてこんなことに」
「ねぇ、ほとり。向こうに見える広いものは?」
クォーツが指差した。
「上に見える青が空。下に見える青が海」
「そらとうみ……」
そこの二つだけは、誰もここにいなくとも変わらずあり続けていた。
「空は天井がなくて、どこまでも高く飛べる。海には、たくさんの水がある。でも、しょっぱくて飲めないんだよ」
そうは言ったものの、ほとりは上の空だった。自分のいない間に何があったのか、考えてもわからない。
天を仰ぎ見ているクォーツから、寮と学舎に視線を移す。
無音で、もぬけの殻の建物というだけで不気味に感じられた。
――みんな、どこに行ってちゃったの。
――今は、いつなの。
――インボルクの浄化は、行われてしまったの。
――新しい島ができて、そっちにみんなで移り住んでるの。
住み着いた蝶
ガサガサッと植木の物陰から音がした。
誰かいるのかと歩み寄り、生け垣から顔を出す。
「誰かいるんですか?」
しかし、そこには誰もいなかった。ほとりとクォーツは顔を見合わせ、気のせいかと首をかしげた。
また、ガサガサッと音がした。
再び、振り向く。
突然、植木の向こうから破れた羽の蝶人が一体飛び上がってきた。
「ジョーズイ、ジョーズイ」
腐死蝶だった。
さらに声を聞きつけた腐死蝶が、二体三体と増え、ほとりたちに襲いかかってきた。
ほとりは、羽を開こうと、首筋に意識を集中しただけでは羽は開かなかった。
片手を首の後ろに持っていこうとしたが、抱えているベレノスの光が傾いて落ちそうになり、すぐに抱え直す。
「ほとり、後ろにも蝶が――」
ほとりが振り向くと、蝶ではなく、腐死蝶たちが二人を取り囲んでいた。
そして、腐死蝶がいっせいに襲いかかってくる。
その時、ほとりの肩にとまっていた同じ蝶が、どこからともなく、群れで現れ、ほとりとクォーツを包み込む。
腐死蝶たちは、何が起きたのかわからず、その場で言葉にならない声を発していた。
あっという間に、視界が真っ暗になるほどに覆われ、腐死蝶の声も聞こえなくなる。
ほとりを呼ぶクォーツの声も消えた。
おかえりなさい
一瞬、無になったのかと思うと、すぐに意識に光が差す。
体中を覆っていた蝶が、はたはたと体から離れていき、辺りに拡散していくと、いつの間にかその姿は見えなくなっていた。
すぐ隣で、クォーツも剣を握り構え、体を強ばらせたまま目をつぶっていた。
「クォーツ。もう大丈夫だよ。目を開けて」
ほとりは優しく声をかけると、クォーツは片方ずつ目を開いた。
「ほ、ほとり。さっきのはいったい――あれ、ここは?」
蝶に包まれた二人は、セリカ・ガルテンとは別の場所にいた。今までほとりが巡ってきたどの島とも違っている。
目の前には、黒い山がまるで塔のようにそびえ立つ。
背後は崖で、風が強く吹きつける。その下は、荒れ狂う真っ黒な海が広がっていた。
垂直の黒い山肌を一匹の蝶が滑空し、こちらに向かってきた。
「またさっきの?」
クォーツが怯えて言う。
「違う――」
腐死蝶とは羽の形も色も違う。しかし、それに見覚えのあったほとりは、別の恐怖を覚えた。
それが確信に変わると、背筋が凍った。
「おかえりなさい、ほとり」
目の前に現れたその蝶人は、ツバメだった。
ほとりは、ベレノスの光を抱えていた手に力が入った。気を抜くと、震えた手から落としそうになってしまいそうだった。
着地したツバメが、にこやかな表情を見せ、一歩一歩近づいてきた。ほとりには、その表情が笑っているようには決して見えていなかった。
また、突き落とされるのではないかという恐怖が、体を動けなくしていた。
「ナイアも戻って来れなかった場所から、よく戻って来れましたね、ほとり。また新しい蝶人を救って来たんですか?
ほとりは、本当に優秀な予言の子」
眼鏡を指であげたツバメに、ほとりは細い視線で見つめられた。
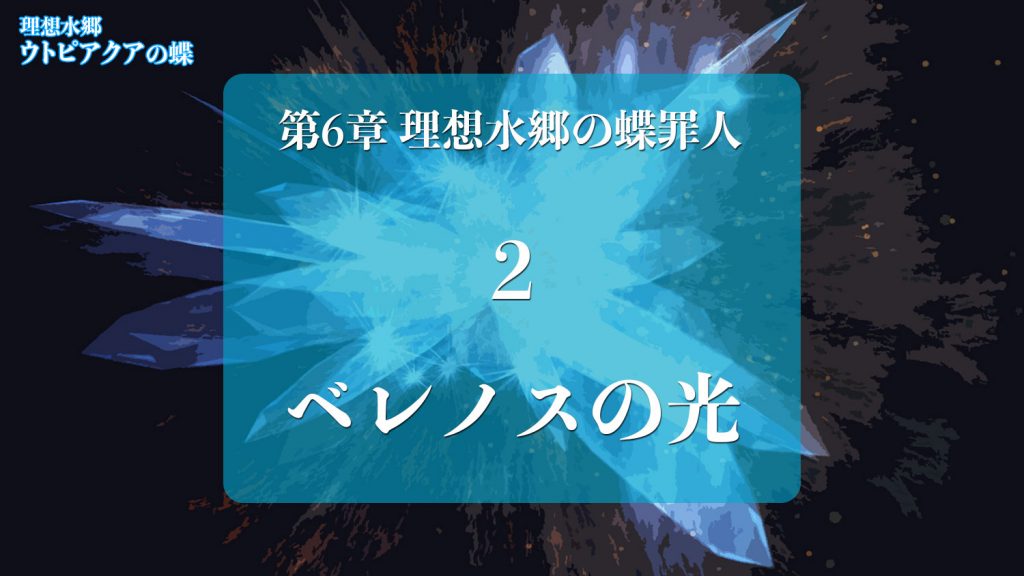
6-2.ベレノスの光


