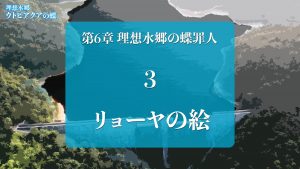当ブログは「note」に移行します。
新しい投稿は「note」にアップしています。
フォロー、ブックマーク、RSSでの登録、よろしいお願いします!
6-3.リョーヤの絵 [小説 理想水郷ウトピアクアの蝶]

声をかけられて、ほとりが目覚めた場所は、黒い水が溜まるダム湖だった。
しかし、その場所一帯から抜け出すことはできず、一人で暮らす蝶人リョーヤと出会う。
砕かれたガラス瓶
ほとりは、仰向けで意識を失ったまま、黒い水面に浮いていた。
わずかな波に流されて、岸に辿り着く。
「こんなところに人が……」
離れたところから女の声。
砂を蹴って、駆け寄ってくる足音。
すぐ近くまできた足音は止まり、波がゆるやかなに打ち寄せる音が聞こえてくる。
穏やかな水の上を漂っていると思っていたほとりは、はたと、それが夢だと気づく。
「ちょっと大丈夫?」
ほとりは、現実世界に意識が戻るように、ゆっくり目を開ける。ほとりと同じくらいの年齢の少女に顔をのぞき込まれていた。
「気がついた? 大丈夫? どっからやってきたの?」
「え、あ……」
まだ頭がはっきりせず、ほとりはゆっくり上半身を起こす。黒い水を含んだ服から、さーっと水分が抜け、本来の天姫の白い生地が蘇った。
「そういえば、私……」
意識が完全に戻ったほとりは、先刻までの記憶がフラッシュバックし、慌てて、腹部を見返した。
服に穴が空いていたが、お腹には一切の傷はなかった。
――刺されたはずなのに。
肩に掛けていたガラス瓶の袋に膨らみがなかった。海で落としてしまったのか。しかし、袋にも穴が空き、ガラス瓶は袋の中で、粉々に砕けてしまっていた。
「そんな……」
唯一、元の世界に戻れる希望が壊れてしまっていた。ツバメに刺された時に、一緒にガラス瓶ともども刺されたのだと、ほとりは気づく。
しかし、どうして体には傷がないの、疑問に思った。
――もしかして、ここは死後の世界?
「おーい」
振り向くと、少女にきょとんとした顔で見つめられていて、ほとりは、また我に返る。
よく見れば、セリカ・ガルテンの制服を着た少女だった。
「ここは、ウトピアクアですか?」
「そうとは言えないかな。ま、こんなところにいるのもあれだから、こっちにおいでよ」
彼女は、意味深な笑みを浮かべ、砂の上を歩きだした。
ほとりは、水から上がろうとして、初めて辺りを見回した。
そこは、山に囲まれたダム湖で、湖は墨汁が溜まっているかのように黒い。見つめていると、深い闇の湖に引きずり込まれそうだった。
空は、薄雲ではっきりしない淡い水色の空が広がっている。まるで、天井に絵が描かれているように止まって見えた。
――ここはいったいどこ。
蜘蛛手良夜と絵
案内された場所は、湖畔に建てられた手作り感満載の小屋。シリカの住処よりは、大きく立派だった。
中には、描きかけの絵や作りかけの立体物ばかり。すべてが中途半端で、生活感はない。
「私は、
窓際に出された小さな椅子に座ると、彼女が言った。
「はい。蜘蛛手、良夜……さん。もしかして、ニタイモシリにいたあのリョーヤさん?」
ほとりが聞いた。
「えぇ、そうよ。あなたもニタイモシリに?」
「はい――」
ほとりは、自己紹介とこれまでの経緯を話した。
良夜は、特段、理想水郷やインボルクの浄火の話に興味を示さず、ただ静かに聞いているだけだった。
「でも、そこへ戻りたいんです。インボルクの浄火に、私が何かできるかわからないんですけど」
ほとりは、刺された場所が少し痛くなったように感じて、手で押さえた。
「残念だけど、戻ることはできないよ。ここは時間が止まった場所だから。
私はここにどのくらいいるかわからない。でも、私の姿がまったくかわらないからさ。
それに、ここから出ることもできない。本気で出口を探したこともないけど」
良夜は言った。山はどこまでも山で、抜けられる気配はない。ダムも形としてあるだけで、水を流す装置はない。張りぼてだとも言う。
「そんな――それじゃ、ニタイモシリにいたのは」
「昨日のことのようだけど、ずっと昔なんじゃないかな。少しすれば、いろんなことがどうでもよくなる。あきらめることを教えてくれる場所さ」
良夜は、まるで人ごとのように答えた。
「ただ、ここに人が来たのが、ほとりが初めてだからさ。ウトピアクアのことなんて、忘れていたよ。
私にとって理想水郷とか、最初からどうでもよかった。でも、ニタイモシリは好きな場所だったよ」
良夜は、笑った。
「どうして、そこからいなくなったんですか?」
「新しい絵を描きに出たんだ。でも、描き終えてすぐ、私はたぶん、殺された。気づいたら、湖の上に浮いて、ここにいたってわけ」
「じゃぁ、私も……」
ほとりは腹部に手を当てる。
「そうかもしれないけど、体はあるし、ここには何もないけど、それなりに自由に生きれるよ」
ほとりは、深く息を吐き出した。
視線を移した先に、描きかけの絵があった。
「絵は、途中なんですか?」
「んー、自分でもどうしたかったのか、わからないんだよね」
白い部分が多く、筆のかすれた跡が目立つが、闇雲に引いたものではないと、ほとりには思えた。
良夜とほとりは、その絵の前に立った。
「大事な物を閉じ込めたいはずだったんだけど、それがなんだったのか」
「出来上がった絵が見てみたいです」
ほとりが聞いた。
「ここにはないんだ。ここで描き上げたものは一枚もない。
誰も見ないし、描かなくてもいいやと思って、筆を湖に投げ捨てちゃった」
良夜はあっけらかんと言った。確かに、筆が一本もなかった。
「完成作品が見たかったです」
「ほとりは、絵に興味があるの?」
「え、はい。絵を描かなきゃいけない時に、こっちに来てしまったので」
「そうだったんだ。無事に最後の絵が残ってるなら、セリカ・ガルテンに置いてあるはずだったけど。
ほとりは、目にしてないのかな、炎と水の絵」
良夜は、思い出しながら言った。
――炎と水の絵。生徒会室に飾られていた絵だ。
「それなら、見たことあります。あの絵、良夜さんの絵だったんですね。
ということは、本当にずっと昔の……」
「だから言ったじゃん。それにあれは、描き残しておきたい光景だったからさ」
――本当に想像で描かれたものではなかったんだ。
「どうしたら、あんな生き生きとした絵を描けるんですか」
「今の私には、残酷な質問だな」
良夜は苦笑いを見せた。
「筆があれば、描けますか」
「描けるかどうかはわからないが、ないよりは描ける確率は上がるだろうけど、描ける自信も保証もないよ」
「それじゃ、筆を探しましょう」
ほとりは、笑顔を見せた。

6-4.闇の底の希望