当ブログは「note」に移行します。
新しい投稿は「note」にアップしています。
フォロー、ブックマーク、RSSでの登録、よろしいお願いします!
2-9.理想のかたち [小説 理想水郷ウトピアクアの蝶]
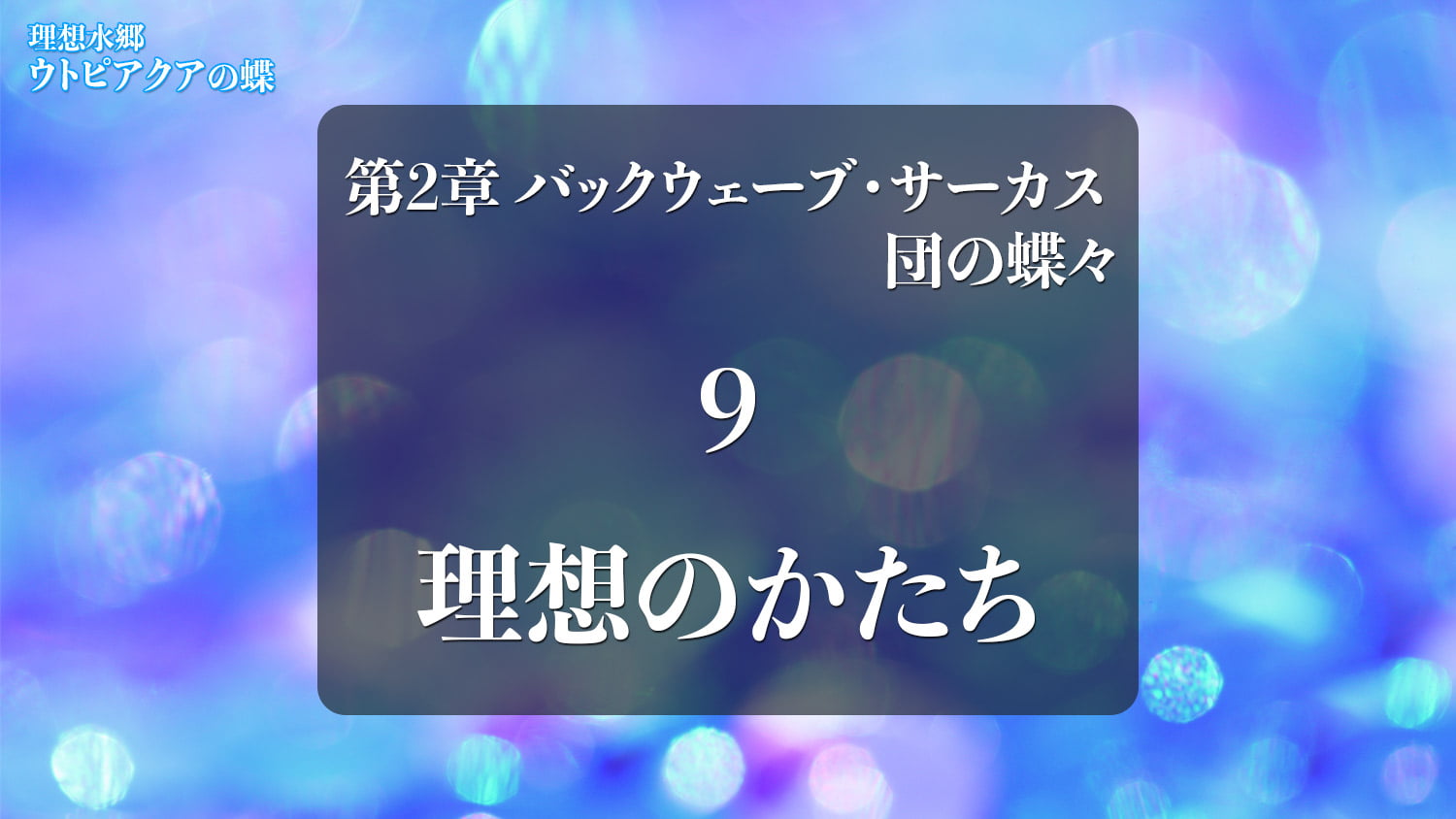
そこに現れたミクロスは、ほとりが再び戻ってくる算段をつけていて、マルコを連れ出す準備をしていたと言う。
予言の子に託すミクロスの思いにほとりは……。
ミクロスの思い
背伸びをして、ドアノブから手を下ろした小さな調教師ミクロスが、部屋に入ってきた。
「無事、戻ってこれたようだな」
「あ、あなたは……ミ、ミク」
「ミクロスじゃ」
「ミクロスさん。これはどういう」
ほとりが、目の前を通り過ぎていくミクロスに聞いた。
ミクロスは、荷物だらけの机に持っていた物を置く。その一つにガラス瓶の水筒であることにほとりは気づいた。
「あ、それは」
「水筒だけは、見つけてきてもらえたが、お前さんが着ていた制服は、捨てられてしまって取り返すことができなかった。すまんな。
いいか、暴れてくれるなよ」
ミクロスは、ほとりに近づきながら腰に差していたナイフを抜いた。そして、ほとりを縛っていたロープを切った。
「ありがとうございます。でも、どうして」
「静かに。ここはステージの裏だ。ほぉ、水汚しの方に行かされてはいなかったようだな」
ミクロスは、汚れていないほとりの作業着を見て、頬をゆるませた。
「あの」
「わかっておる。フリークかもしれない者が紛れていると言えば、必ずお前さんは戻ってくるとわかっていた」
「だったら、なんでわざわざ……」
ほとりは、捕まえられる前にかばってくれれば良かったのにと内心吐露した。
「時間が必要だった」
「時間?」
「予言の子が出現したことをフィロに伝える時間と段取りのな」
「フィロ?」
「フィロメーナ・バックウェーブ。ここの島主じゃ」
「ショーの終わりに出てきたあの人……」
マイクを持って水の宣伝をしていた女性をほとりは思い出した。
「そうだが、あれは興業側の者がフィロに化けているだけでな、本物は老体で床に伏しておる。
もうフィロの力では、実質経営者を制御することはできない。
フィロもわしも、マルコをずっとこのままにしておくのが心苦しかった。そこにお前さんが現れた」
「でも、予言の子と言っても、何か力があるわけじゃなくて……」
「お前さんの力となってくれるシュメッターを助けに来たのじゃ。詳しくは知らないが、フィロがそう言っておった。
新しく生まれるウトピアクアのためにも、どうか、マルコを……。
いや、ララ・クランシーをもっと広い空に羽ばたかせてやってくれ」
ミクロスは背を正して、頭を下げた。
「ララ・クランシー?」
「マルコの本当の名前だ」
「素敵な名前。でも、ララさんは本当にここを出たいと思っているんですか?」
「お前さんたちが現れてから、心は揺れている。利用されていることも心の内では知っている。かわいそうに子供ながらにな」
「でも、どうやって連れ出せば」
「そこはもう段取ってある。そろそろ時間がなくなってきた。お前さんは、これに着替えろ」
ミクロスは、机の上に手を伸ばし、つかんだ物をほとりに渡した。
ほとりがそれを広げると、マルコがフリークショーで着ていたような青色の衣装だった。
「こっちじゃ」
ミクロスは、ほとりを積まれた箱の物陰に連れて、そこから去った。
「え、本当に、これに着替えるんですか?」
「なんだ、小さかったか?」
「いや、そうじゃなくて、どうしてこれに?」
「すべての目を欺くためだ。お前さんの仲間にも段取りを知らせておる」
「ユーリにも?」
ほとりは、手にした衣装を見つめると、ユーリのニヤけた企み顔が思い浮かんだ。
「時間が迫っておる。早くせい」
ほとり自身、工場を出てからのことは考えていなかったため、その通りにする他なかった。
目指した理想
「着替え終わりました」
箱の陰からほとりが出て行くと、ミクロスに上から下までマジマジと見られて、ほとりは恥ずかしくなった。
明るい青色で、キラキラと宝石と見間違うような小さな粒が散りばめられていて、腕を動かせば、ヒラヒラがなびく。
「おぉ、似合っておるぞ。懐かしい。フィロの若い頃を思い出す」
「若い頃?」
「わしは、フィロとともにこのウトピアクアで、ショーをしていた。その時のフィロが、目の前にいるようじゃ」
「それじゃ、ミクロスさんは、この島の水のことは全部知っているんですか?」
「あぁ、知っておるよ。一部の関係者だけしか知らんが」
「これで本当にウトピアクアと言えるんですか? これが理想水郷だなんて認められない」
ほとりは、ミクロスを上から見下げる。
「幸か不幸か、知恵を持ったシュメッターたちによってここまで大きく発展してしまったウトピアクアは、簡単には止められなくなった。
わしらにも生きる場所が必要だった。
だが、興業のために唯一シュメッターとして成長させられたマルコだけは、せめて、いつか本来の役目に向き合ってもらいたいと思って、世話役をわしがかってでた」
「でも、それは、フィロメーナさんが、責任をもって理想水郷を作り続けていれば――」
「そう言ってやるな。理想とは簡単に口にできても、それを形にすることはそう簡単じゃない。
これまでやってきたことを推し量ることもな」
壁の向こう側から、ひときわ大きな拍手と歓声が響いてきた。そして、いっきに静まりかえると、奇妙な音楽が鳴る。
ほとりも一度聞いたことのある音楽。フリークショーが始まる時のものだった。
ミクロスは、机の上の水筒を背伸びして取り、ほとりに手渡した。
「もうここへは戻ってこれないからな」
「ありがとうございます」
ほとりは水筒の紐を肩に通し終えると、唐突にミクロスに手首をつかまれ、無理矢理部屋から連れ出された。
「ちょっとミクロスさん。どこへ?」
「お前さんとマルコをここから逃がすため、ひと芝居うってもらう」
「ひと芝居って?」
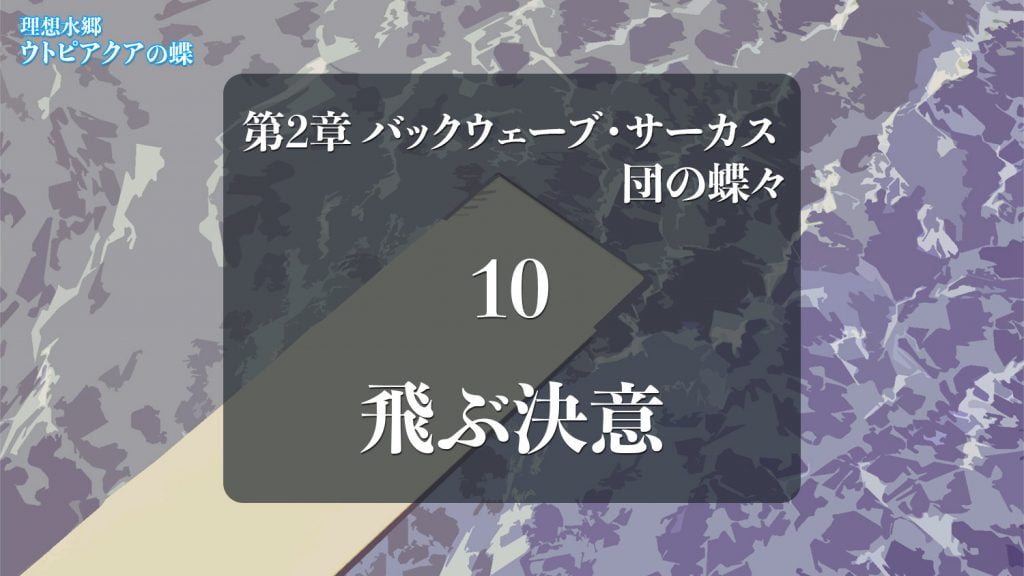
2-10.飛ぶ決意
更新のお知らせを受けとる
SNSをフォローしていただくと、小説の更新情報を受けとることができます。


