当ブログは「note」に移行します。
新しい投稿は「note」にアップしています。
フォロー、ブックマーク、RSSでの登録、よろしいお願いします!
2-1.汚れた水郷 [小説 理想水郷ウトピアクアの蝶]

ゲートの先のウトピアクアは、水と空気が汚れていた。
囚われたシュメッターを探しに町にいくと、ほとりが持っていた水筒の水を、突然男が捨ててしまう。男は、バックウェーブの水だけが、正しい水だと言う。
汚い水と空気
光のカーテンをくぐった瞬間、空気が変わった。
腐ったような異臭がほとりの鼻をつんざいた。
うっ、と、口元に手を当て、辺りに目をやると、同じ洞窟が続いているかのように暗く、ずっと先に丸い出口らしきところが光っていた。
とにかく新鮮な空気が吸いたいと、ほとりは出口に向かって走り出した。
外へ出ると、どんよりとした雲が広がっていて、目の前は大きな川で、濁った水がゆっくり流れていた。
ほとりは振り返ると、大きな排水管が口を開け、それが川沿いに沿っていくつも並び、黒い水がじゃばじゃばと流れ出ているところもあった。
空気が動いている分、臭いは薄れたが、時折、異臭の塊が流れてくる。
ほとりは、腕で顔半分を覆う。セリカ・ガルテンを出る時に、明日架から着ていくように言われた紺のコートがマスク代わりになった。
昼間のようだが、雲が厚いのと灰色の空気で暗い。
黒い煙を上げて、荷を積んだ船が川を渡っていく。向こう岸には、工場が建ち並び、いくつも立つ煙突から、遠慮とはほど遠く黒い煙が空へ吐き出されていた。
そんな空を誰も飛んでいない。
ほとりは土手を上がっただけで、息が苦しくなった。ここの空気をなるべく吸いたくなかった。
砂だらけの公園が広がり、完全に枯れた木がところどころに立っている。まるで、黒と灰色しかない世界だった。
――ここのどこが、理想水郷なの。いったいどうしてこんなに。
ほとりは、無性にその原因が知りたくなった。
まずは、助け出さなければならないシュメッターを探しにいくため、公園を横切って、大きな建物が建ち並ぶ町の中心へ向かった。
ほとりは明日架に、町の中心に行けばすべてがわかる、と言われて、それ以上詳しいことは聞かされていない。
ツバメには試練と言われた最初の理想水郷でのミッション。ほとりにとって、何もかもが想像を覆されていた。
正しい水
町並みは、ひと昔前というより都会的ビル群が荒廃して時間が止まったようだった。
道路に面した通りは、店が並んでいて、どこも飲み物や軽食を売っていた。その多くは、コーヒーや酒屋ばかりだった。
行き交う多くの大人が手に瓶や紙コップを持って、ことあるごとにそれを口にしていた。中には、ふらふらと足下がおぼつかない人もいたりする。
ほとりは辺りの様子を見ながら歩いていると、肩にかけていた瓶の水筒を横から急に引っ張られた。
「お嬢さん、お嬢さん、この水筒に何を入れてるんだい? 正しい水かい?」
顔が赤く、視線も姿勢もおぼつかない酒瓶を持った年配の男性だった。
「この中に何が入っている?」
「た、ただの水ですけど……」
ほとりは、戸惑いながら答えると、また急に、男が水筒の蓋を開け、逆さまにして中に入っていた水を地面に捨てこぼしてしまった。
「えっ、ちょっと」
突然のことでほとりは呆気にとられ、水筒を奪い返した時には、ほとんど残っていなかった。
水筒から手を離すと、緩んだ紐が重力で引っ張れたが、数秒前の重さはそこにはなかった。
「どこのかわからない水なんて持ち歩いちゃいかん。あー、かわりにとっておきをくれてやる」
年配の男は、もたつく足で最寄りの露店に近づいていく。
「それを、一番でかいやつで」
男は、ワイシャツ姿で腰にエプロンをつけた露店主に注文をした。
大きな紙コップになみなみとつがれたコーヒーが出てきて、ほとりは手渡された。湯気がたち、香りは良かった。
「ここのはうまいぞ。出所のわからない水なんか飲むより、コーヒーや酒を飲め。安全だ」
私の水だって――と、ほとりは、手渡されたコーヒーを見やる。香りこそコーヒーだが、茶色く濁った液体が、川の水を思い出させる。
「味は、わしが保証する。飲め」
年配の男と店主の視線に負け、そっと一口飲んだ。苦味が口の中に広がるが、のど奥から鼻に香りが抜けていく。あの川の水を使っているわけではなさそうだった。
バックウェーブの水
「お嬢さん。生水は人が飲むものではない。ありゃー、ニワトリかフリークショーの奴らが飲むもんだ。体に毒だ」
ほとりは、男の言っていることが理解できなかった。
「みなさん、水を飲まないんですか? このコーヒーも水で出してますよね?」
「水は飲まん。コーヒーも酒も煮沸した水で作るんじゃ。生で水を飲むとしたら、バックウェーブで売っている水だけだ。あれだけは安全だ。そのコーヒーもここらの酒も全部バックウェーブの水からしか作られておらん」
「バック……ウェーブの水?」
「バックウェーブの水じゃ。知らんのか?」
男は驚いたように、強い口調になった。
「は、はい。私、ここに来たばかりで、教えてくれますか?」
露店主は、ちらりとほとりを不思議そうに見つめ、ほとりは視線を返すと知らぬ顔で仕事を続けた。
ほとりは、しまった、と思った。
ここも島であるなら、そう大きくもなく隣町はないかもしれない。ただ、陸を分断するような川向こうにも大きな町もあったから、変に勘ぐられたりしないだろう。
「なんじゃ、そうか。なら仕方あるまい」
その男は、酒に酔っていることもあって得意気になってくれた。
「いいか。この通りを行くとな、もっと大きな通りに出る。左に曲がって北上して、突き当たったところにバックウェーブ・サーカス団のテント小屋がある。
そこの興行主が毎日公演終わりに水の販売をしておる。それがバックウェーブの水じゃ」
「誰でも買えるんですか?」
「サーカスを見た者だけだ。その日の新鮮な水を売ってくれる。それが世界で唯一安全な水じゃぞ」
「どうして安全だとわかるんですか」
ほとりが聞くと、男に酒の匂いが香ってくるほど顔を近づけられ、細い目で見つめられた。
「変なことを聞く子じゃ。そんなのサーカスを見たらわかる。もし、バックウェーブ以外の水を飲んじまったら、フリークになっちまうからな」
「フリーク?」
「人だが、人じゃない姿になっちまうんだ。あんな姿になりたかねぇ。お嬢さんも醜い姿になりたくなければ、バックウェーブの以外の水を飲むな」
「人じゃない姿ってことは、もしかして羽の生えた人とかいたりしますか?」
「なんじゃ、知ってるんじゃないか。お嬢さんもサーカスを見に来たんか」
「え、えぇ」
「いるよ。蝶の羽を生やした少女が……。フリークは、この世のものではなく恐ろしいが、あのマルコの幻想的に舞い飛ぶ姿は美しい」
ほとりは、それだと心の中でぐっと拳を握った。
話しを続けたそうな男の話しを上手く切り上げ、礼を言ってその場をあとにした。
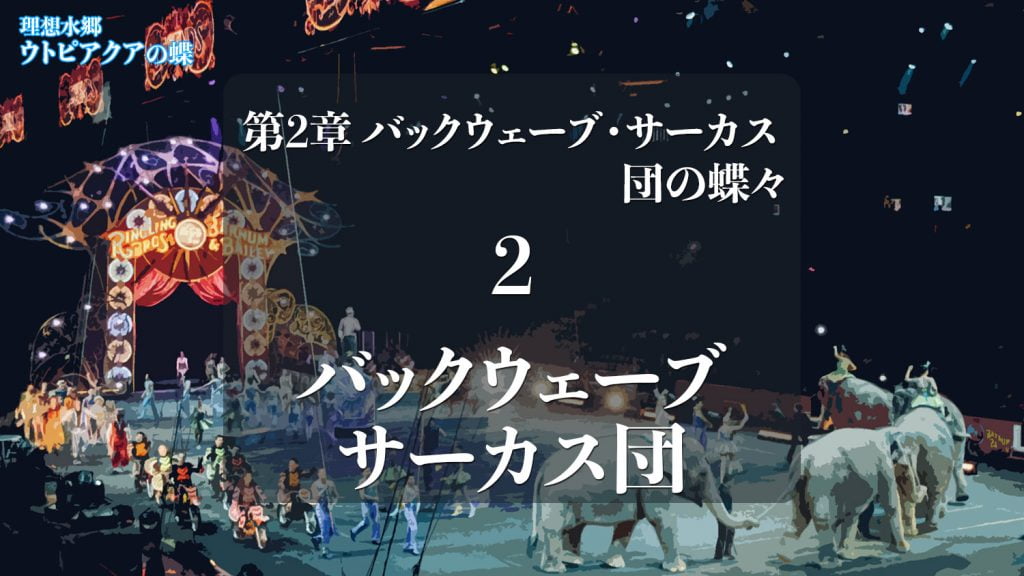
2-2.バックウェーブ・サーカス団


