当ブログは「note」に移行します。
新しい投稿は「note」にアップしています。
フォロー、ブックマーク、RSSでの登録、よろしいお願いします!
2-2.バックウェーブ・サーカス団 [小説 理想水郷ウトピアクアの蝶]
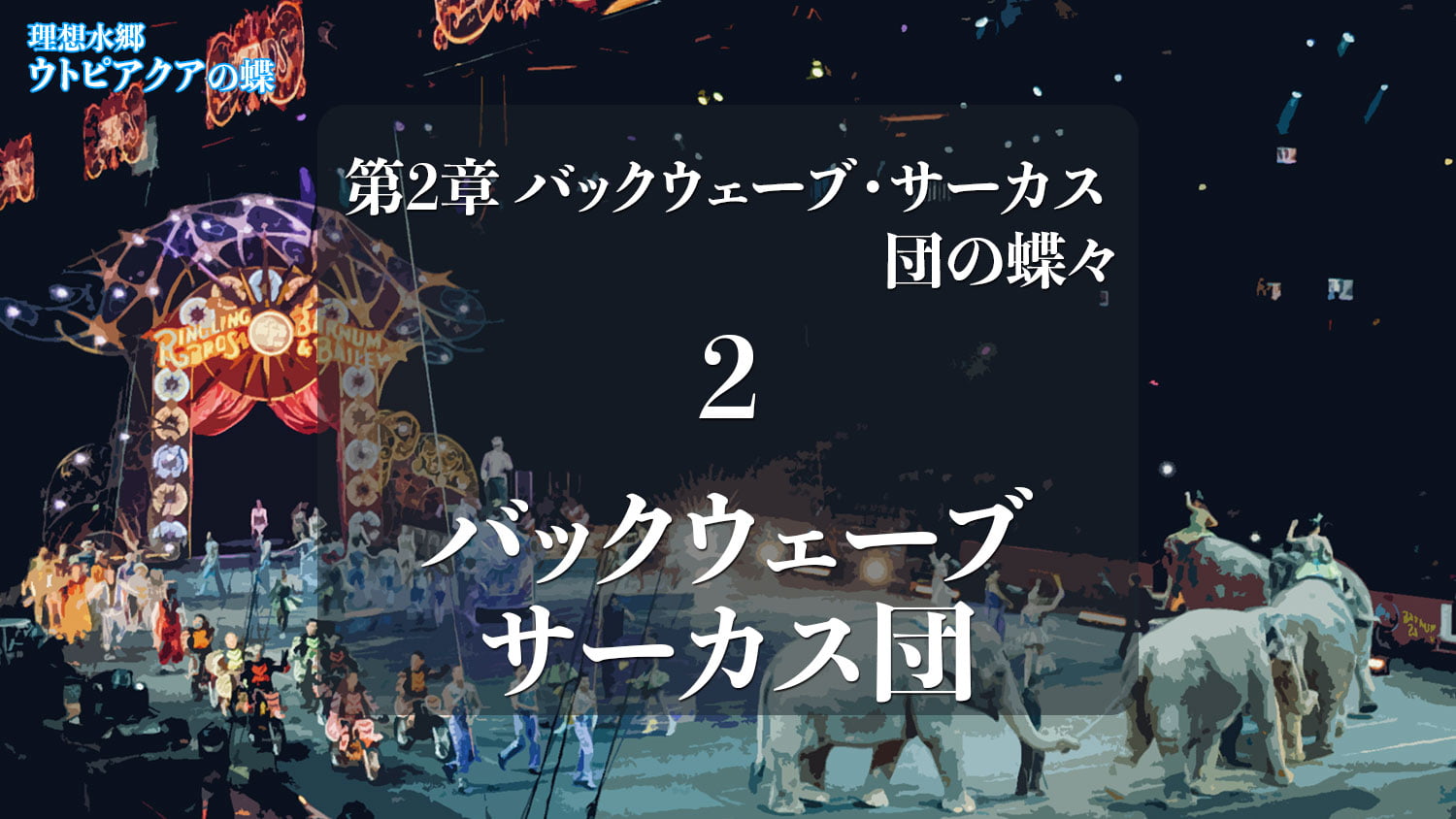
大通りを走る車は黒い煙を上げていて、誰もが咳き込んでいた。
羽を生やした少女が写るサーカス団のポスターに導かれ、ほとりは大きなテント小屋に到着。サーカスショーが始まる。
町中のポスター
ほとりは、年配の男に言われたようにまっすぐ進んでいくと、大通りに出た。
さらに人の流れが増え、ここが島とは思えないほど大きな島であることを感じた。
車が勢いよく黒い煙をあげながら行き交っている。元いた世界の文明ほどではないが、発展していることがうかがえた。
ほとりは、煙を吸って、咳き込んだ。
通りを挟んで並ぶ大きな建物で、空気が流れず沈んでいる。周囲の人々も咳き込みながら、慣れたように歩き去っていく。
その誰もが、カップやボトルを持ち、ことあるごとにそれを口に運んでいた。
やはり、ここの通りの店々もコーヒーや酒を売っている。男が言っていたバックウェーブと書かれたラベルの水も販売されていた。
それらを見る限り、販売されている飲み物は、安全なのだろうと思えた。
ほとりは、手に持っていたコーヒーで、喉を洗い流して、口元をコートの袖で押さえた。
これが本当にウトピアクアなのかと、辺りを見回しながら大通りを進んだ。
――このウトピアクアの長は、一体何を考えているのだろうか。私は、こんなウトピアクアは嫌だ。
しかし、ほとりはどんな理想水郷がいいか、まだ明確には言えずにいた。
ショーウィンドーに貼られたポスターが目につき、速まる足を止めた。
紫色をベース背景にサーカス団のテント小屋やショーに出る人たちが配置され、その上からバックウェーブサーカス団の黄色い文字が描かれていた。
ポスターに写る人たちは、年寄りの男が言っていたような人物は見当たらない。演技をしている熊やライオンと言った動物はいた。
ただ、唯一、蝶の羽を生やした少女が空を飛んでいた。しかし、その羽も衣装の一つかのように見え、あまり違和感がなかった。
――この子が、囚われているシュメッターリングか。
公演時間は、毎日夕方から満員になってからと書かれていた。
通りには、同じようなサーカス団のポスターが何枚も貼られていて、まるで、テント小屋に導いているようだった。
テント小屋
大通りを真っ直ぐ進んでいくと、白と黄色が交互になったテント屋根が見えてきた。近づけば近づくほど、視線は上がっていく。テントの高さや大きさも桁違いに大きかった。
開演にはまだ時間があるというのに、多くの人が入場口から鉄柵に沿って列を伸ばしている。
ほとりはその最後尾に並んだ。すでに入場は開始され、敷地内の物販テントには人だかりができているのが外からもわかった。
少しずつ列は進む。
周囲の会話に聞き耳を立てていると、マルコという単語をみな口にしていた。
入場受付で、百五十ユーアを支払った。事前に明日架から二千ユーアを手渡されていた。
ほとりはここの相場がわからなかったが、安いと思えた。サーカス団の運営は大丈夫なのか心配になったが、入場を待つ列の後方を見ると、ほとりが並んでいた時より伸びていた。
続々となだれ込んでくる人の流れに乗って、ほとりは物販テントにやってきた。
飲み物や軽食も売っていたが、コーヒーか酒類しかなかった。そして、水は小さな紙コップで、無料で配っていた。
そこの人だかりは膨らんでいくばかり。
ほとりはグッズのテント前にやってきた。中でも、シュメッターの写真が数多くあった。小さいサイズのものから壁にかけられるほど大きな額に入れられた写真まで。少女が羽を広げて宙を飛んでいる姿が写っていた。
クールに撮られたその写真は、確かに美しく見えたが、そこに彼女の笑顔の写真は一枚もなかった。
ほとりは押し流されるまま、テント小屋の入り口から遠い場所へとやってきてしまっていた。小屋の裏手が見えたが、柵があり、それ以上先には進めなかった。
しかし、人の声や動物の鳴き声が時々聞こえてくる。柵の間から見えるずっと先に、スタッフが準備に追われる様子も見えた。
――きっとあのシュメッターもここのどこかに。
ショーの始まり
テント小屋への入場が始まり、馬蹄形にステージを囲む客席は、すでに半分ほど埋まっていたが、テント内は熱気に包まれていた。
ほとりは、ステージの左側の後方の席に座ることになった。ステージを一望できるが、見下げる形で遠い。
しかし、自分と同じくらいの目線に、ステージの装置が見えた。空中に吊るされた通路がステージの反対側と向かい合うように設置されていた。
気づけば、席は満席で熱いほどだった。
ショーが始まると、大きな音楽と色とりどりの照明がステージを照らす。
ジャグリングに始まり、ピエロの玉乗りといった子供向けとも思える演目が続く。
小さな狩人姿の調教師とともに、熊やゾウ、ライオンを連れてきては次々と演技をさせた。そのたびに、拍手と声援がステージへと飛ばされる。
動物がステージからいなくなると、今度は多くのパフォーマーたちが出てきて、重力を感じていないかのようにステージを縦横無尽に動き回る。
ほとりの目線の先にあった天井近くの通路からは、空中演技が行われ、離れ技がきまれば、会場内は割れんばかりの拍手に包まれた。
パフォーマーがステージから消え、拍手も一段落すると、会場が静かになった。次の何かを期待する観客の鼓動が聞こえてくるようだった。
「早くフリークショーを始めろ」
「フリークを出せ」
「蝶のフリークだ」
男たちの乱暴な声が上がり、客席がざわつき始めた。
それが合図だったかのように、照明が暗くなり、さっきまでとは違う奇妙さをうかがわせる音楽が始まった。
そして、ゆっくりと紫色の照明がステージを照らし出した。
ほとりは、息を飲んだ。
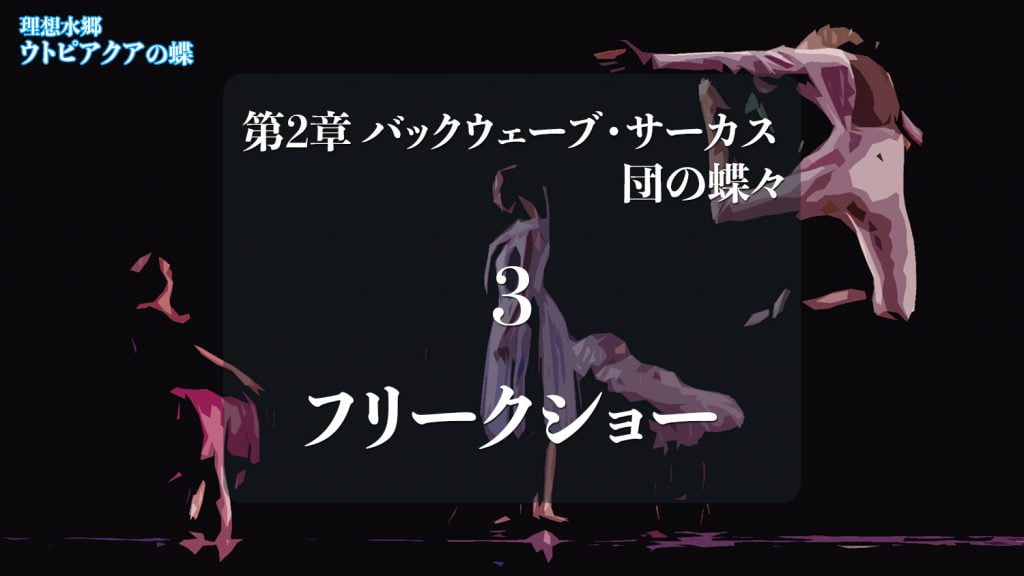
2-3.フリークショー


