当ブログは「note」に移行します。
新しい投稿は「note」にアップしています。
フォロー、ブックマーク、RSSでの登録、よろしいお願いします!
6-5.ルサルカの少女と精霊 [小説 理想水郷ウトピアクアの蝶]

その声は、ほとりにしか聞こえなかった。水の羽を持った者。それは、ルサルカの少女。理想水郷を救う者。
十二の精霊とともに、ほとりは宙を飛び、燃え盛る島へ向かう。
ルサルカの少女
ぬーっと、濃い青の影が、様々な青を遮って、頭上を覆った。
細長くもあり、太くもあるそれがゆっくりと頭上を動いていく。
ほとりは、それに恐怖を感じることはなかった。
――また、理想水郷を救いたいと思っているのか、ルサルカの少女よ。
「またって、どういうことですか?」
ほとりが、頭上の影に向かって言った。
「ほとり? 誰としゃべってるの?」
突然、顔を上に向けて声を出したほとりに驚いた良夜が聞いた。
「良夜さん、声が聞こえませんでしたか?」
「えっ、私は何も」
「たぶん、あの青い影が声をかけてきたんです」
ふたたび見上げたほとりを真似るように、良夜も顔を上げた。
――インボルクの浄火のあと、お前は、自分にされた仕打ちを恨んではいないのか。
「ほら、今、聞こえました?」
ほとりが、人差し指を上にむけた。
「全然、何も聞こえないよ。ほとりにしか聞こえてないんじゃない」
「えっ」
ほとりは、そこで初めてゾクッと震え上がって、良夜に飛びついた。良夜の体温に触れて、自分の背中の冷えたさに気づく。
「ほとり、驚かさないでよ。なんて言っているの? 聞き取れるの?」
「う、うん」
ほとりは、良夜の腕をつかんだまま、聞こえたままを伝えた。
「それって……」
良夜は、少し考えて続けた。
「誰かと勘違いしているんじゃないないかな。まぁ、誰かとは言わないけど……」
良夜の片眉が意味ありげに上がった。
「ど、どういうことですか?」
――覚えていないのか、自分のされた仕打ちを。
「何なんですか、仕打ちって」
――落とされたんじゃないのか、地底に。
「えっ」
ほとりは、ツバメに落とされたことを思い出した。地底への穴に。
「でも、私は……」
――水の羽を持ったルサルカの少女はお前だけだ。
「それは、ナイアじゃ……」
――お前は、ナイアじゃないのか。
トクンと、ほとりの鼓動が強く打つ。
「いいえ、違います。私は、浅葱ほとりです」
ほとりは、ゆっくり視線を落とした。
――だが、水の羽を持つルサルカの少女は、一人。お前だ。
――水の羽を持っているからって、飛べもせず、私に何ができるの……。
――それでは、理想水郷を救いたくないというか。
ほとりは、声を出していないのに、心の声を聞かれて驚いた。
「理想水郷を救いたい。でも、本当に救いたいのは、ベレノスの光を使った蝶人を……救いたい」
また顔を上げて、心を込めてほとりは言った。
良夜は、口をきっと閉め、ほとりの心を察するように、静かにほとりを見つめている。
――同じことだ。理想水郷とは、環境であり、そこに居るモノだ。どちらが欠けてもなりたたない。
「はい……でも、私に何ができますか」
――飛べないことなど問題ない。ルサルカの少女。その力を使う資格が、おまえにはある。
「ルサルカの少女の力」
ほとりは、脳裏に生徒会室で見た青い絵が蘇った。そして、それを描いた筆を持つ良夜を見た。
荒れ狂う海とされた絵。
でも、それは水が踊っているように見えた。誰かと愉快に踊っているように、決して驚異な力などではなく、恵みの水のように。
――インボルクの浄火は、すでに始まっている。遅れてしまえば、取り返しのつかないことになる。
「どうしたらいいの」
――ルサルカの少女よ。おまえには、私を含め、十二の精霊を操ることができる。
ほとりは、どこかでルサルカの少女が十二の精霊とともにやってくることを聞いていた。
――急いで浮上しろ。精霊がおまえにつく。そうすれば、おまえにはすべてわかる。
――急げ。
十二の精霊
ほとりは、そう言われても不安だった。
何が起こるのか、何も想像できない。しかし、セリカ・ガルテンに来てからずっと、全部そうだった。それでもこうして、今ここにいる。
唯一、わかっていることは、理想水郷を、みんなを、救うこと。
ほとりが意識を上に向けると、良夜ともに包み込んでいる水の球が浮上していく。
得体の知れない濃い影が、真上からいなくなり、青々揺れる水中を水の球が上昇する。
そして、水の球がすーっと上昇を速め、どんどん加速していく。
ほとりは、そんな意識を羽に送った覚えはなく、速度を制御できず、怖くなった。
良夜が手を握ってきた。あたたかかった。
「大丈夫。味方が、私たちの足下にいる」
良夜に言われて、下を見ると、頭上にいた青の濃い影が、水の球を押し上げていた。
それがわかった瞬間、ほとりは安心した。自分の足元に支えてくれるものがいるという安心感だった。
上昇すればするほど、頭上からの青い光は薄らいで、水面を泳ぐ白い光が落ちてくる。
――水を出たら、羽を広げよ。おまえは、私とともに飛ぶ。
ほとりは、一度息を飲み、頷いた。
濃紺の影は、海面を盛り上げ、突き破り、しぶき上げて、そのまま宙へ飛び上がった。
ほとりは、自分たちを包み込んでいた水の羽を広げた。
「な、なに」
突然、自分たちの足下や一帯が明るくなった。
足下の巨大な青い影の左右から、ほとりと同じように光の羽が生えていく。
周囲を見渡すと、他にも羽を生やした大きな濃い青の影が左右に並んで、一方向を向いて飛んでいる。その巨体の前頭部には、白く縁取られた黒い目らしきものあり、どれもほとりを見ていた。
「ははっ、これはすごい。絵に描いただけじゃ伝わらないね」
良夜は、一瞬でその場を理解して笑っていた。
光の羽を生やしたその大きな影の輪郭を目でなぞるほとり。
「クジラ? 羽が生えて飛んでる」
――そうだ。十二の精霊は、おまえの意思で動く。海の水も。意思を送れば、動かせることを知っているだろ。
足元の一番大きなクジラの精霊が言った。
「うん」
髪がなびき、天姫の白い羽織もなびく。しかし、それを気にすることなくほとりは正面を向いた。
視線の先には、夜空と周囲の海面を赤く染める燃えあがった島が見えた。
そこには、二体の炎の巨人がゆっくりと歩き、小さな炎の蝶たちが、大地を燃やし舞っていた。
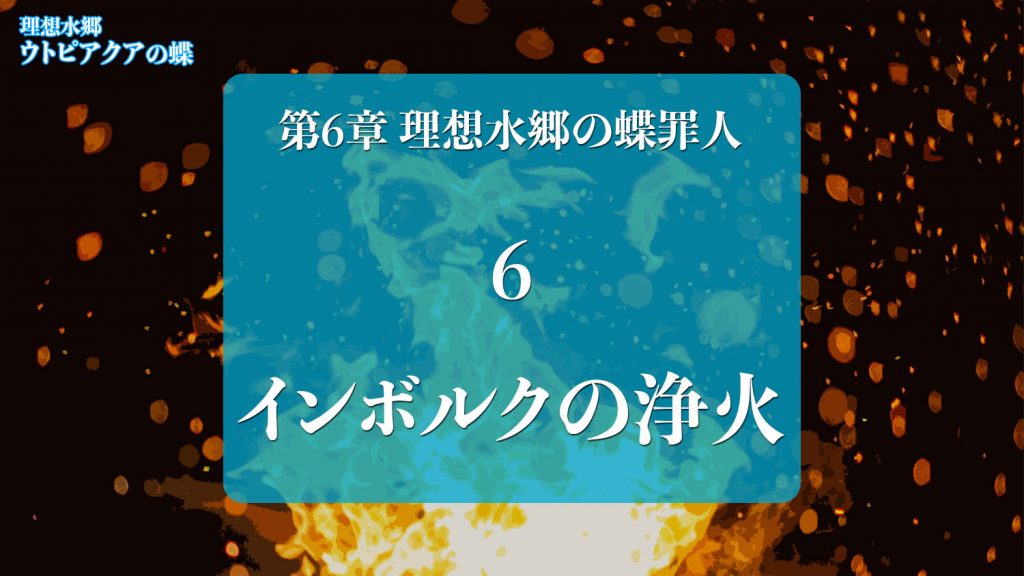
6-6.インボルクの浄火


