当ブログは「note」に移行します。
新しい投稿は「note」にアップしています。
フォロー、ブックマーク、RSSでの登録、よろしいお願いします!
一文物語365 2017年10月集

一文物語
1
その日も大労を終えた仕事びとたちが、誰もいない自宅でカバンを開けると、見知らぬきれいなハンカチが入っていて、誰かにねぎらわれているかのように思えて、みんな涙をそれで拭って、湿っぽい夜を過ごしていた。

2
時間が止まって欲しいと願う人の時は虚しく流れ、時間が止まった人は、儚く、動かない。
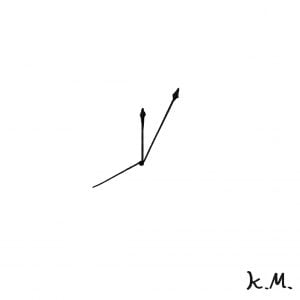
3
空工場の高く伸びた煙突からは、こねられた青く広がる空気が浮かび上がっている。
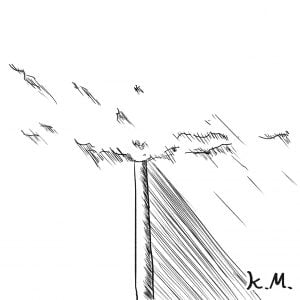
4
好きだった都会を離れて田舎に住むことになった彼女は、あの頃を忘れられず、緑や茶色の景色を全て灰色に塗り上げてから、カラフルな色を入れて楽しんでいる。
5
昔、悪いことをした彼は、一人一人謝りに行く旅に出たが、誰一人そんなこと覚えている人はおらず、再会のたびに酒の花を咲かせたが、旅の終わりに、やっと見つけたと後ろから声をかけられた。
6
全く印象に残らなかった旅行から帰ってきた彼は、ターミナルの空港や駅にある自動販売機で、旅先に近い場所の思い出缶を買って摂取し、ないことをあったことのように思い出して旅を終えた。

7
体重が増えていくと悩む彼女の外見は全く変わらないが、彼への思いが日に日に増していっていた。
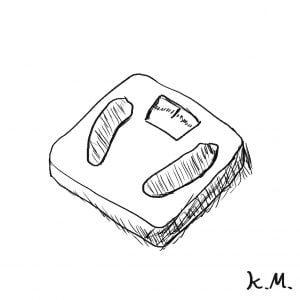
8
姿を消した名探偵は、密室に閉じ込められて餓死していた。

9
メモしたノートにペンを挟んで閉じておいたが、翌日それを開いてみると、メモの続きから自分しか知らない過去の恥ずかしい出来事が赤裸々に書かれていて、目も当てられない。
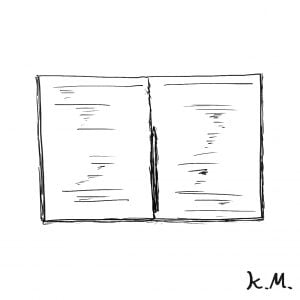
10
携帯電話にメモしておいたものが、翌日になるとその続きに、自分しか知らない人を助けた過去の経験が書き足されていて、電子回線を通して一晩で世界中に知れ渡り、全世界が感動して泣いていた。

11
慌てて締切日を書いた紙にはあらゆることがメモされていて、それを書いた人はとっくに死んで、後世になって、それが世界の終わりを示す予言書として解読が進んでいる。

12
目覚まし時計の音が遠ざかっていく。
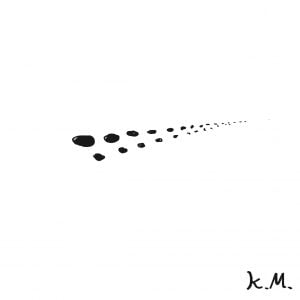
13
残り一枚のティッシュを箱から引き抜くと、舌が引き抜かれたかのように激痛が走る。
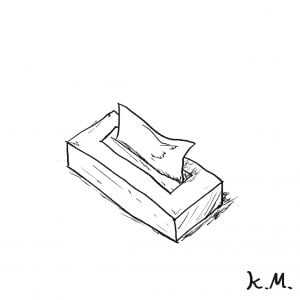
14
手違いで天国から地獄へ送られたお人好しの彼は、マグマの流れる場所を住めば都だと称し、その熱で湯を沸かして天獄温泉の営業を始め、数々の極悪人の魂が天へと昇って行った。
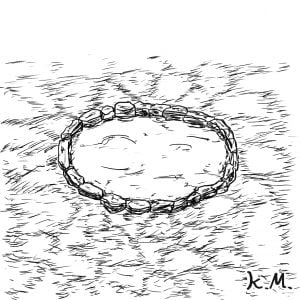
15
その小説全集に収められている文字たちは、もっと仲間を増やして欲しいと思っていたが、すでに作者は亡くなっていることを知り、次々と作者を探しに夜の闇に溶け落ち、本は死んでしまった。
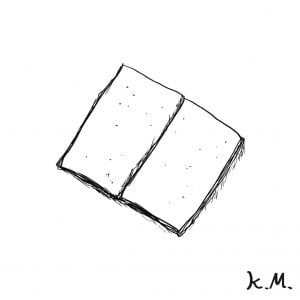
16
古くから地を守る霊山に、怨念を祓う絶世の美女がいると噂が立ち、ひと目見たいと悪霊を宿した男どもが次々と山を登って帰って来ず、崖っぷちで払い落とされている。

17
道もない山中で迷ってしまい、少し大きめの花びらを目印として一枚一枚落として歩いていたが、とうに腹は減り、人の歩いた痕跡か、ポテトチップスが前方へと続いている。
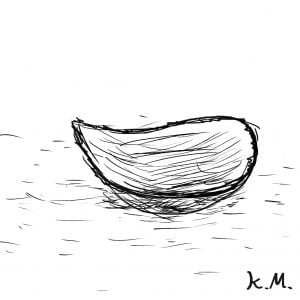
18
死者のホテルは満室で遺体を預け置く場所がなく、例の山のふもとにそっと横たわらせ、行き場を失った死者が彷徨いいなくなる。
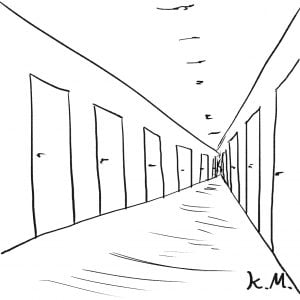
19
熱帯夜で浅い眠りの中、薄らかに目を開くと、ひと鉢の植物が部屋中に鬱蒼と生い茂り、緑の密度に押しつぶされた夏の災厄から外に出れず、とうとう冬が近づいてきた。
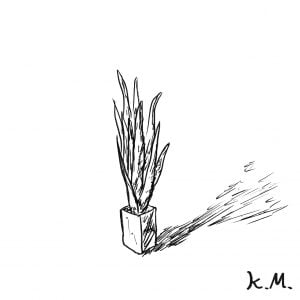
20
荒くれ者たちの乗る船が、ついに新大陸母なる大地に到着し、盛大に宴を開いたその晩、母に抱かれたようにみな、静かに眠りに落ち、大地と一体化して母の中へと還っていった。
21
罪に耐えきれなくなった男は、無断で建物に登り、一糸まとわぬ姿で、自分を包み隠さず犯した七つの大罪を演説のごとく話し始めたが、大罪よりも無断侵入と公然を乱したことで、警察にこっぴどく怒られるだけだった。

22
自由から逃げて、ただただ金庫番をしていたが、ふとそれを持ち去ってしまいたくなる。
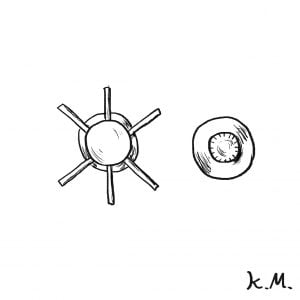
23
愛情に飢えた少女が、見ず知らずの青年に誘拐してと頼んだが断られ、近くの大きな川に飛び込もうとすると、彼は必死に少女の体を押さえつけた。
24
銀河を超えてやってきた信号を解析すると、将棋の次の一手だとわかり、こちらも次の一手を送り返すやりとりが数年続き、とうとう地球は侵略されてしまった。
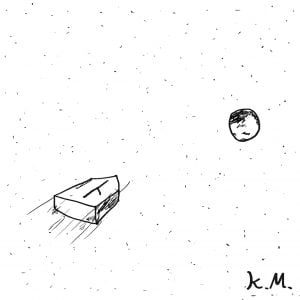
25
殺された国語教諭は、国語入試問題必勝法という分厚い本で殴打されており、当時同じ場所にいた生徒が、なんとしてでも勝ちたかったと述べ始めているという。
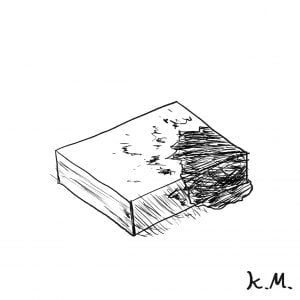
26
塔のように切り立った崖の頂上に、同時に到着した男二人がチャンピオンの名をかけて、狭い足場で押し引き合うバランス対決の死闘を繰り広げている。

27
墜落論を語るには、実際に落ちる感覚をつかめばなるまいと、研究者の二人が塔のように切り立った崖の頂上に登ると、一人の男が倒れていて、ひとまず試験落下を行うことにした。
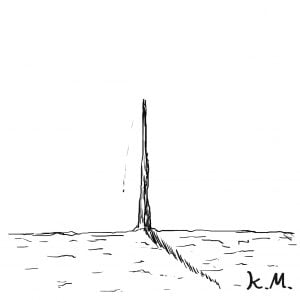
28
夜に開園するその動物園では、どこで拾ってきたかわからない月に照らされ、動物はみな、骨の姿で過ごしており、来園者は、ちらっと窓ガラスに映る骸骨姿の自分に悲鳴をあげる。

29
一週間に一度しか開かないそのお店の前には、暗い雰囲気の長蛇の列ができ、一週間分の笑顔を薬のように購入して帰って行く。
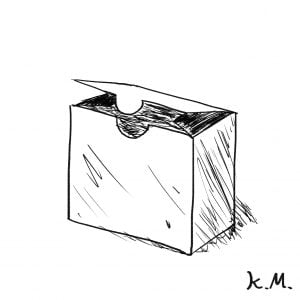
30
熱を持たないはずの電子文字があちこちで燃え上がり、ついに手元のガラス板も炎を上げて火傷をする人が続出し、しばらく落ち着いた言葉が飛び交っていた。

31
猫によって、大いに甘やかされ、人類最後の日を終えた。


一文物語365の本
2017年10月の一文物語は、手製本「舞」に収録されています。




