当ブログは「note」に移行します。
新しい投稿は「note」にアップしています。
フォロー、ブックマーク、RSSでの登録、よろしいお願いします!
1-3.蝶の羽 [小説 理想水郷ウトピアクアの蝶]

光に飲み込まれたほとりは、空から落ちていた。次第に迫る地面に、死を覚悟する。
そして、目の前に緑色に光る納屋で見た蝶が現れ、ほとりの背中にも羽が生えていた。
宙に溺れる
ほとりは、光に飲み込まれた瞬間、納屋の床が抜けたように落下していた。
ボーボーと耳元で空気が流れていく音が鳴り、目を開けるのもつらく、怖かった。
そっと目を開くと、層になった雲が次々と、上昇していく。
そのかわりに、眼下に青く広がった海がゆっくりゆっくり近づいてくる。
パラシュートでもあればと、一瞬頭をよぎったがそんなものを身につけた覚えは当然ない。
ほとりは、このまま海面に激突して死ぬんだと悟った。
視界に緑色に光るものが映った。
――蝶。
ほとりと一緒に落下しているはずなのに、ほとりの目の前を優雅に飛んでいる。
蝶は死の象徴だと、本で読んだことを思い出したほとりは、もう死の世界に足を突っ込んでいるのだと思った。
しかし、それは黒い蝶ではなかったかと思ったその時だった。
「うわっ」
突風が吹いて、ほとりの体が大きく揺さぶられた。
ほとりは、瞬時に、自分の体に違和感を覚えた。体をあおられただけではない。まるで背中で広げた布に風がぶつかったようだった。
ほとりは首を後ろに回した。
バサバサと髪が暴れる背後に、まるでキラキラと光を反射する水面が広がっているように見えた。
これも死の世界の現象かと思いながら、その水面の縁をなぞり見ると、蝶の片羽に見えた。
目の前を飛んでいた光る蝶と同じ形をした羽。
薄い透明な皮膜の中には、水が入っているように、光を反射している。
ほとりは、反対側に顔を向ける。そこには左右対称の羽があった。
――私の背中に、羽が生えている?
いったいどうしてこんなものが、と考える一方で自分の状況が気になって、視線を下
に戻す。
ついさっきまで広がっていた海の青がより青く、小さかった島がもう目の前にまで迫っていた。
夢か幻か。生えた羽で空を飛べるならと、ほとりは背中に意識を送り込むが、羽は動いてはくれなかった。
もうこのまま地面と激突して死ぬんだと、ほとりは思った瞬間、全身が冷たくなった。
それが恐怖だとわかった。
死ぬのが怖かった。
地面と激突した時は、痛いのか。
体はぐちゃにぐちゃになってしまうのか。
考えれば考えるほど、冷や汗が出て、血が青ざめていくように冷えていく。
次第に視界も白く見ずらくなって、意識が薄れていく。
――このまま気を失えば、きっと。
水を得た蝶
耳元で暴れていた風の音が、遠ざかって消えてなくなった。
意識を失ってどのくらいか、一瞬か。
耳元の音が歪んだ。
ゴボゴボと大きな気泡がいっきに上がっていく音。
時が止まったように静かになった。
目が覚め、目を開けていくと、ぼやーっとした視界が広がっていく。
ひとつ息を吐くと、目の前をコポコポっと空気が昇っていくのを見て、後悔をする。
空気のかわりに口に入ってきた水は、しょっぱかった。慌てて口を押さえると、ここが水中にいることを理解させた。
地面との激突は逃れたが、今度は息ができずに溺死すると、ほとりはすぐに悟る。
痛いか苦しいか、違いはそれだけで死ぬことには変わらない。
水面は、遠くで光を反射してほとりを呼んでいるようにも見えた。
ほとりはそこまで泳いでいける自身はなかった。足のつかない場所で、どうやって上がっていけばいいのかわからない。
体を動かせば、このまま沈んでしまうのではないかと。
しかし、水の中は、ほとんど流れはなく、ほとりは宙に浮いているようだった。
――く、苦しくない。
意識が戻ってから、三十秒以上はたっているのにも関わらず、呼吸はしていないはずなのに、息苦しさがまるでなかった。
体も軽かった。
まるで空にでもいるよう。飛んでいるところを想像すると、ふわりと体が勝手に水中を移動する。
水が、ほとりを避けているかのようだった。
ほとりには、その原理がわからない。
だが、自然と背中の羽が羽ばたき、魚の尾ひれのように、水を強く押し出していた。
空飛ぶ妖精のごとく、魚になったかのように、ほとりは水中を自由に泳いだ。
泳げない自分が泳いでいる感覚は、夢を見ているように不思議だった。
だが、ほとりのいるそこは円柱に掘られた土壁に囲われていて、向かうは水面しかない。
少女蝶々
ほとりは、外の光を揺らめかせる水面から、そっと顔を出した。
宙に二人が浮いている。蝶の羽をゆっくりと羽ばたかせながら、ほとりは見つめられていた。
辺りからは、女性たちの不穏な声が聞こえてくる。
水が貯められた縁には、やはり数人の女性たちが集まっていて、ほとりを見ていた。その人たちには、蝶の羽はない。
「君、大丈夫?」
宙にいた一人が、恐る恐る近づいてきた。長い金髪で、大人びている顔立ちの女性だった。
ほとりは、どう答えていいか迷っていると、一瞬、上を黒い影が横切った。
「はーい、どいてどいて。ケイト」
頭上から猛スピードで、黒い影が降りてきた。ケイトと呼ばれた金髪の女性が、すっとほとりから離れた。
水面ぎりぎり、ほとりの目の前に、ふわりと舞い降りた。大きな黒い蝶の羽を生やし、黒髪の長い女性だった。
ケイトとは違った清楚さのある大人っぽさをまとっていた。
「ようこそ、セリカ・ガルテンへ。私のシュメッターリング」
彼女は、笑顔でほとりに、手を伸ばしてきた。
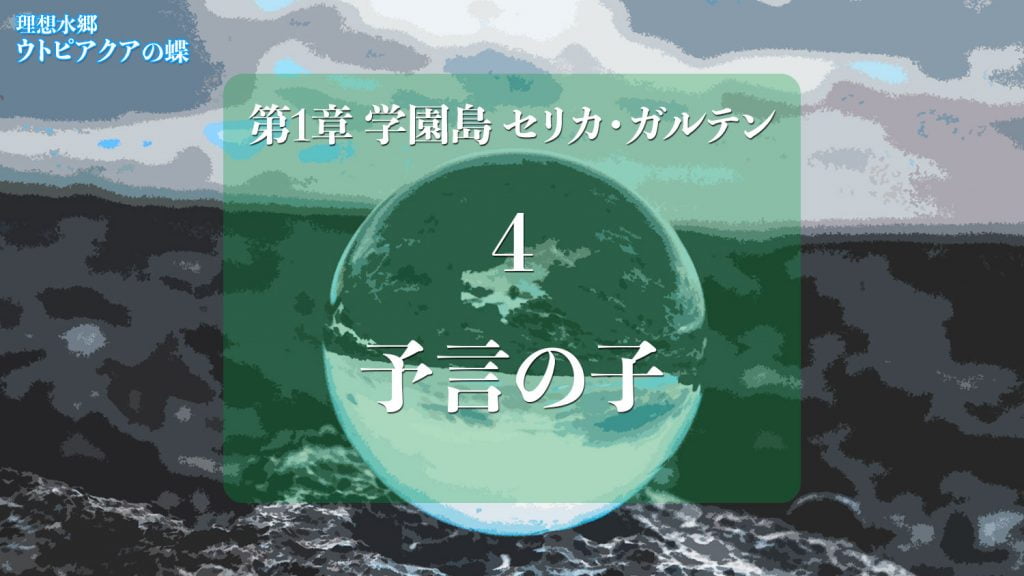
1-4.予言の子
更新のお知らせを受けとる
SNSをフォローしていただくと、小説の更新情報を受けとることができます。


