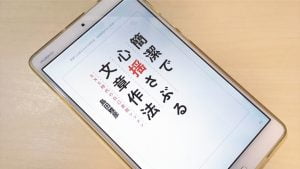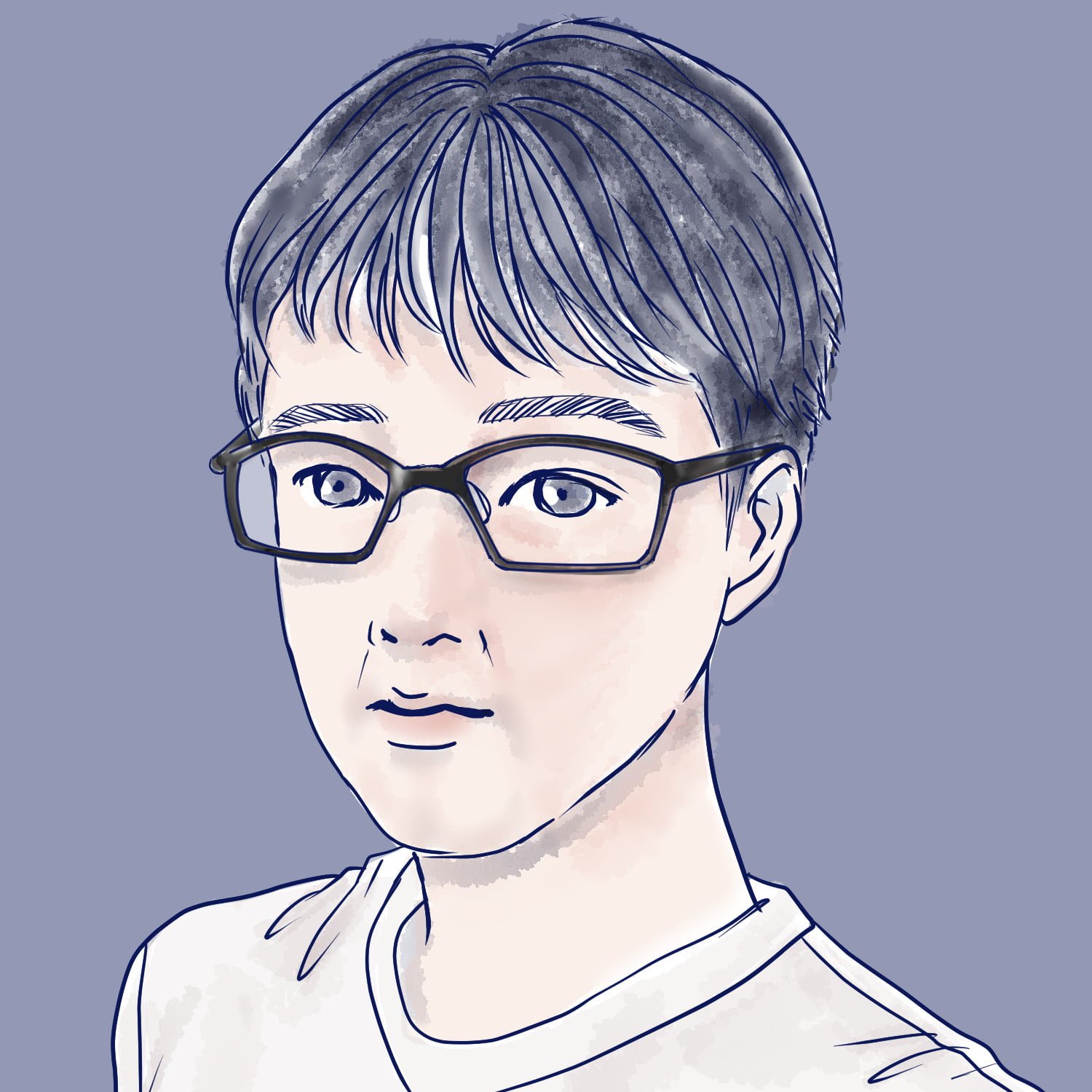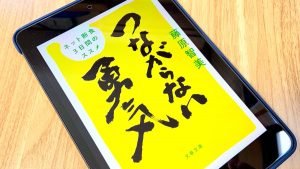当ブログは「note」に移行します。
新しい投稿は「note」にアップしています。
フォロー、ブックマーク、RSSでの登録、よろしいお願いします!
「つながらない勇気 ネット断食3日間のススメ」著:藤原智美 を読んで、メディアはメッセージ、「ことば」を使い分ける必要がある!
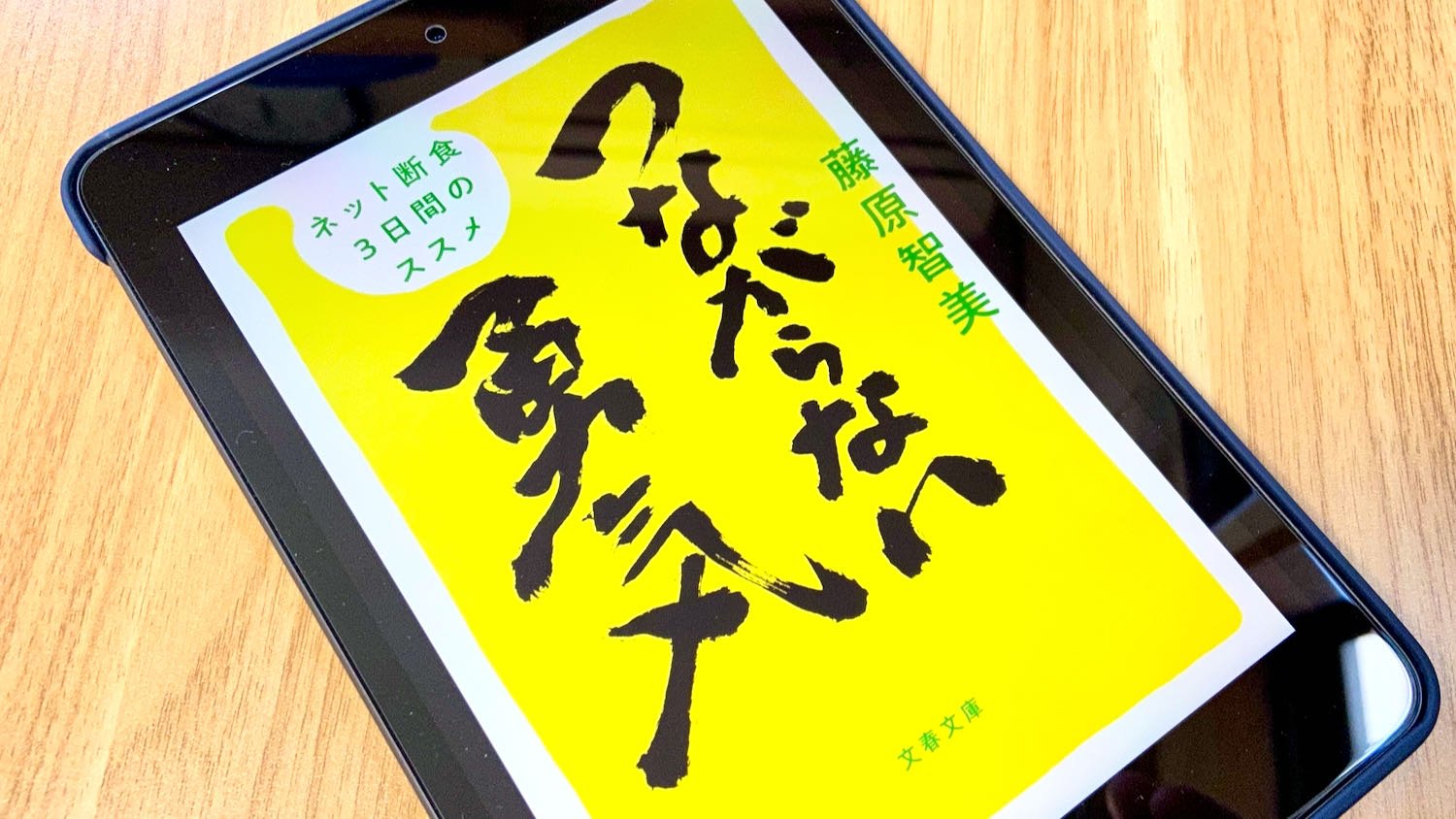
「運転士」で芥川賞を受賞した作家・藤原智美さんの本。
「つながらない勇気 ネット断食3日間のススメ」とタイトルにあるので、てっきりネットにつながらない効能やその影響が書かれている本だと思っていました。
実のところ、「ことば」が各時代でどう使われてきて、インターネットが主流になった現代で「ことば」の扱いがどう変化しているのか、詳しく解説された本でした。
タイトルから想像していた内容とは違ったのですが、身近に使用する「ことば」について思った以上に学ぶことができました。
印象的だった内容をご紹介します。
テーマと目次構成
本書のテーマは、3つ。
- ネットの普及によって紙に記される「書きことば」が急速に衰退ている
- 国や経済のあり方、人間関係、思考そのものが根本から変わろうとしている
- ネットをはなれて「読む」「書く」が必要なこと
- 序章 ことばが人と社会をつくる
- 第一章 ことばから狂いはじめた日本
- 第二章 五〇〇年に一度の大転換
- 第三章 消えていく日本語
- 第四章 人も社会も変えるネットことば
- あとがき
- 文庫版追補 第五章 書物から得る「つながらない勇気」
「ことば」の歴史をふりかえりながら、「ことば」が時代時代の社会や人間関係を作ってきたのかが解説されている。
作家ならではの、「本」というメディアに触れることの大切さも書かれています。
3つの「ことば」が、歴史を作ってきた
- 話しことば
- 書きことば
- ネットことば
話しことば
人々が「文字」をもつ前から使っている声で伝える「ことば」。
「話しことば」は、一音発したら、その「ことば」は消える特徴がある。
文章を書くことに比べて、内容を考える時間は短いこともあげられる。
「文字」が生まれて、「活版印刷」の発明によって文字が印刷されることによって、文書が社会の基盤となっていった。
活版印刷が誕生してからのここ500年間は、文書、本書でいう「書きことば」が時代を制することになった。
書きことば
紙にインクを使って書かれる「ことば」。
「話ことば」と違って、話者が目の前にいる必要がない。情報が書き残されて、時間をとわず、いつでも読み返せる。
「話ことば」をそのまま文字に起こして文章に起こしては、読みにくい。文章の展開が悪かったり、重複していることもあり、説得力に欠ける。
そのため、「書きことば」の体裁があり、より内容を伝えやすくしている。
また、大事なことは文書に書き起こされ、保存された。「書きことば」によって時代や社会、行政を支える基盤となっていた。
しかし、インターネットが現れて、「書きことば」がそのまま「テキスト」に置きかわるわけではなかった。
ネットことば
「話しことば」と「書きことば」の間が、「ネットことば」ではないかと、本書では言う。
しかし、まだ誰も「ネットことば」を体得できていない。
500年の「書きことば」の時代に、唐突に現れたインターネットの影響を受け続けている最中で、「ことば」の大転換中なのだ。
SNSやメッセージのやりとりを見れば、ほとんどが会話形式であるが、文字を使っている。
ここで「書きことば」を使っても、最終的に書いてある内容は理解できても、ネット上のやりとりとして成立しているかを考えるべきだと感じた。
電子的やりとりは高速で、「書きことば」として文字を打ち込むのとは違う。
また、スマホやパソコンのディスプレイに表示される文字は、ほとんどが統一されていて、筆跡のような個人差はない。
どういった「ことば」で、やりとりするのが「ネットことば」なのかは、まだわからない。
メディアはメッセージ
電話やラジオ、TVは、「話しことば」。
紙や本は、「書きことば」。
インターネットは、「ネットことば」だけではない。「話しことば」も「書きことば」も含まれる。
そう、YouTubeにみる動画は、話者が映像に映り、声を発している。
今まで記録しておけなかった「話しことば」が、ネットを使うことで「書きことば」と同じように、記録できてしまう。
2021年には、「Clubhouse」という音声メディアが登場し、場所を問わず、声を誰にでも届けられるようにもなった。
インターネットが現れたことによって今までの「ことば」の権威性が変わった。
メディアによって使う「ことば」が違うのだ。「聞く」と「読む」では、受け取り方は違うだろう。
メディア自身が「メッセージ」で、「ことば」が違えば、「メッセージ」も変わる。
つながらない時間
「ことば」を生む時に、ネットにつながらない方がいい、というのが本書のテーマでもある。
「ことば」は、誰かのものを利用するものではなく、自分から生むものなのである。
ことばにおける「個」の境がおぼろげになっている
ネット上で出会うことばはすべてみんなのものであり、私のものでもあるという感覚
インターネット時代にいるとはいえ、「個」として自律的に考える、内省するという行為は、「書きことば」に向かい合う必要がある。
それは、「どう書くか」を考えさせる。ネットにつながらず、孤立した状態で「どう」の部分を自分で考える必要があると筆者は強く言う。
「書きことば」に向かい合うことで、「個」としての「ことば」を獲得する。
まとめ
ネットが出現したことで、メディアはさまざまな形に変わり、増え続けていく。
そこで使う「ことば」について、とても考えさせられました。
過去、時代の中で使われてきた「ことば」の意味合いや影響を学び、これからどう使っていくのか、その切り口が新しい発見でもありました。
「簡単にことばを使う」というよりは、「メディア」に合わせて意識的に「ことば」を使っていきたいと思えるようになりました。
「ことば」がどう捉えられてきたのか、「ことば」の扱われ方をもっと知りたい人はオススメの本です!